 |
図に実験と計算の結果の比較を示します。左側が実験結果、右側が計算結果です。パラメータは選択されたルート番号およびそれらの合計です。すべてのケースについて左右が一致しています。とりわけ、居室配置の(A),(D)、(G)、次いで分散配置の(B)、(C)、(E)がよい一致を示しています。
分散配置の場合の問題点は、最下層の第2教室という奥まった場所から出て上の中層甲板に入った人たちの経路の選び方が、それ以前に中層甲板にいた人たちと異なっているということです。つまり想像距離が異なり、心理的集団として異質であることです。これは想像距離を変えて繰り返し行ったコンピュータ計算で分かりました。
集中配置の場合、(F)、(H)に見られるようにルート3のピークが計算の方が後ろにずれることです。これはシミュレーション画面を見ていて分かることですが、ルート2に多数が向かっているとき実験では早めにルート3を選択する人があらわれるのに、計算ではルート2の階段が渋滞し始めてからルート3が選ばれ出しています。これは現実には人々はこんなに多くの人がルート2を選べば滞留するに違いないと判断したと思われます。つまり、計算には人々の予見能力が組み込まれていないためです。
現状ではこれらの問題を解決するに至っていません。しかし、多少粗いがシミュレーション計算は実験結果の状況を再現でき、妥当性が確かめられたといえます。
|
|
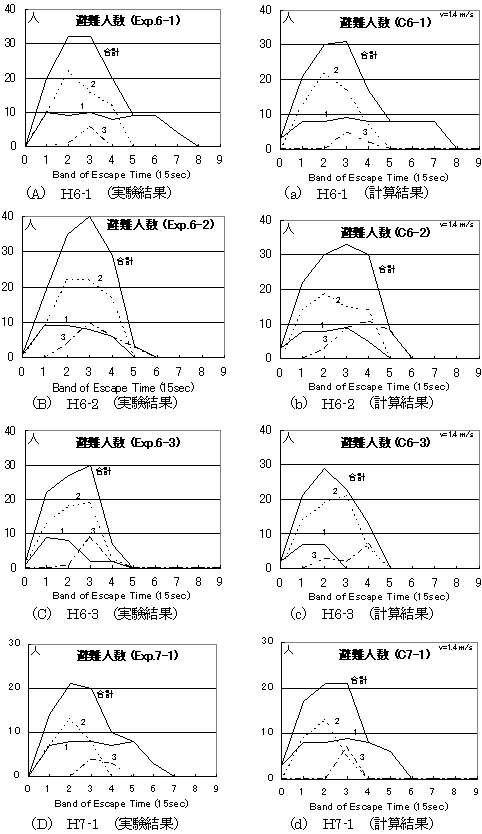
図:実験結果と計算結果の比較(1)
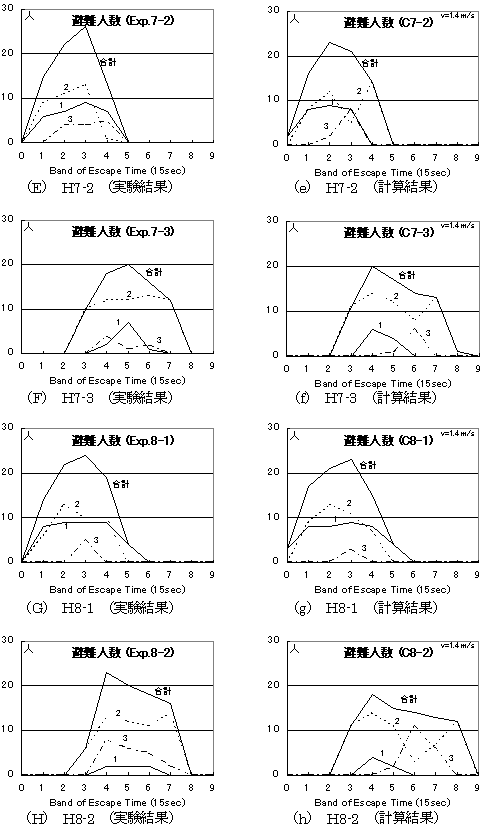
図:実験結果と計算結果の比較(2)
|
|

