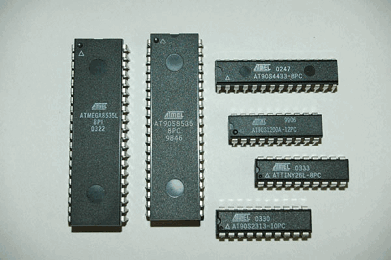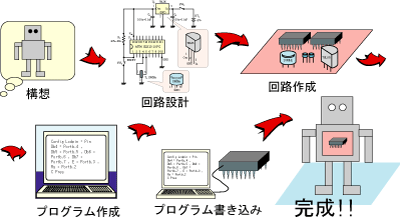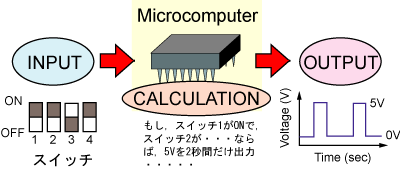|
|
| 講義ノート 機械工学科の学生のための初級メカトロニクス |
 第2章 マイコンの基礎 第2章 マイコンの基礎 |
|
|
| 次章では自らの手でマイコン回路を製作します。マイコン回路の製作を始める前に,マイコンの特徴やマイコン回路に使われる電気・電子部品について理解しておきましょう。 |
|
2.1 マイコンとは
マイコンとは,「マイクロコンピュータ」,または「マイクロコントローラ」の略で,パソコンのように複数の部品で構成された機器ではありません。
マイコンを使うのはそれほど難しいことではありません。簡単な知識を身につけ,簡単な装置を準備するだけで「機械」の高性能化ができるかもしれません。マイコンをうまく使いこなすことができれば,機械作りの幅が広がるのは間違いありません。
|
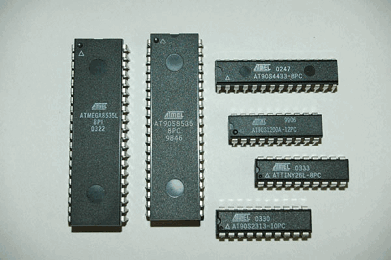
本講義で使用するAVRマイコン |
右図はマイコン機器を開発する流れを示しています。構想からはじまり,マイコン回路の設計・製作,プログラムの作成と書き込みを行います。もちろん,メカの設計・製作も重要です。
|
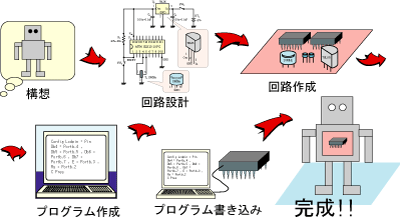
マイコン機器開発の流れ |
|
|
2.2 マイコンの特徴
マイコンの特徴をまとめます。 |
| (1) 小型 |
デジタル入出力やタイマ,メモリの機能が1つの電子部品に含まれています。 |
| (2) 安価 |
1個300円〜1500円程度で購入することができます。 |
| (3) 多種類 |
入出力ピンの数,機能などが異なるものなど,多くの種類のマイコンが市販されています。 |
| (4) 多様なプログラム環境 |
プログラム言語として,BASIC言語やC言語などがそろっています。しかも,中にはインターネット上で無償公開されているフリーソフトもあります。 |
| (5) 書き換え可能 |
昔のICとは異なり,プログラムを何度でも書き換えられます。 |
| (6) 高速 |
シンプルな動きしかできませんが,動作が速いのが特徴です。 |
| (7) 多用途 |
幅広い用途で使用できます。 |
|
|
2.3 マイコンでできること
| マイコンは,外部からのデジタル信号を読み取り,書き込んだプログラムによって何らかの計算をして,外部に信号を出力するのが基本的な使い方です。すなわち,パソコンのように,画像を扱ったり,複雑な計算をさせたりするのには適していません。 |
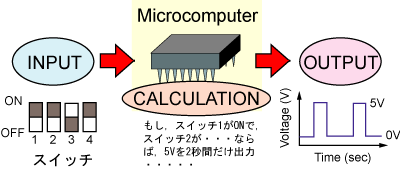
マイコンでできること・・・ |
| デジタル信号だけしか扱うことができないマイコンですが,うまく使いこなすことができれば,モータを自由に動かしたり,電気信号を変換したり,あるいはセンサと表示器をつけて簡単な計測装置を作ることもできます。 |

(a) モータ駆動 |

(b) 信号変換 |

(c) 表示器 |
デジタル信号だけで・・・
|
|
|
2.4 マイコンの性能と用語
マイコンには,性能や機能が異なる様々な種類があります。それらの違いを知るためにはある程度のマイコン用語を知っておく必要があります。以下,代表的なマイコン用語を紹介します。 |
| (1) クロック |
マイコンの動作速度を表す用語です。AVRマイコンの最高動作クロックは,8〜12
MHz程度です。実際の動作クロックは回路に取り付ける発振子(セラロック)の周波数で決まります。特に,モータ制御などではクロック(=時間)が重要になります。 |
| (2) ピン |
AVRマイコンは,端子間ピッチが2.54 mmのIC形状をしています(EIA規格)。その端子(足)をピンと呼びます。5本程度のピンが電源やクロックなどのために使われ,残りがプログラムによって入出力が可能になるピンです。 |
| (3) ROM |
ROM(Read Only Memory)とは,読み出し専用記憶装置のことです。一度書き込まれた情報を読み出すための記憶装置で,書き換える必要のない情報や書き換えられては困る情報を記憶させます。 |
| (4) RAM |
一般にRAM(Random Access Memory)と呼ばれているものは読み書きが可能なメモリ(記憶装置)を示しています。本来の意味は,複数の情報を記録し,記録順,記録位置等に関係なく読み出せるものの総称です。 |
| (5) フラッシュROM |
フラッシュROMはプログラムを書き込むためのメモリです。これが大きいほど,大きいプログラムを書き込むことができます。AVRマイコンでは,1000回の書き込み・消去が可能で,電源を切っても情報は消えないことが特徴です。 |
| (6) A/D変換 |
A/D変換とは,アナログ電圧を読み取り,マイコンで扱うことができるデジタル値に変換する機能のことです。 |
| (7) 分解能 |
分解能は,A/D変換がどれだけ細かく電圧を読み込むことができるかを表す用語であり,ビット数として表示されます。例えば,10ビットの分解能を持つA/D変換とは,測定電圧を10ビット=210=1024に分解できる性能です。0〜5 Vの電圧を測定するのであれば,約0.005 V(=5/1024)刻みで読み取ることができることになります。 |
|
|
2.5 マイコン回路とその構成部品
スイッチのON/OFFに合わせてLED(発光ダイオード)を点灯させる簡単なマイコン回路 |
| (1) 抵抗器 |
| (2) コンデンサ |
| (3) LED(発光ダイオード) |
| (4) 三端子レギュレータ |
| (5) セラロック |
| (6) マイコン |
| (7) ICソケット |
| (8) 基板 |
| (9) スイッチ |
| (10) リード線 |
| (11) 電池/電池ボックス |
|
2.6 マイコン回路の基礎
●決められた端子に,電源を接続する。
●決められた端子に,セラロックを接続する。
●端子を決めて,入力スイッチやセンサを接続する。
●端子を決めて,出力信号(LEDやモータ)を接続する。 |
| (1) 電源回路 |
| (2) グランド |
| (3) セラロック |
| (4) リセットスイッチと入力用スイッチ |
| (5) 出力確認用LED |
|
2.7 プログラムの概要
スイッチのON/OFFに合わせてLED(発光ダイオード)を点灯させる簡単なマイコン回路 |
| (1) パソコンとマイコンのプログラムの違い |
| (2) プログラム言語 |
|
2.8 マイコン回路を開発する要点
★回路や構成部品の基本を理解する。
★構成部品のデータシートを解読できる技術を身につける。
★入力信号はどのようなものか?必要とされる出力信号はどのようなものか?
★どのような計算(プログラム)が必要なのか?
★何のために作るマイコン回路なのかを考え,マイコン回路は「機械」の一部であるという認識を持つ。 |
|
【演習問題】
(1) 現在はマイコンを使用していないが,マイコンを使用することで高性能化が図られる機械を考えなさい。
その構造・原理を図面で表し,機能および高性能化される理由を文章で説明しなさい。 |
|
|
[PREVIOUS] [TOP] [NEXT]
[Koichi Hirata Top Page] [NMRI Top Page] |
|
|