船舶技術研究所ニュース № 19
SRI NEWS
| 基礎研究紹介 Basic research 大ヒットした映画「タイタニック」の沈没シーンでは、巨大なプロペラが海中から現れ、船と共に海中に沈んでいきました。水中にあるプロペラを実物の姿で見ることはなかなかありません。しかし、船には不可欠なものであり、また最も造形美の溢れる装置の一つでもあります。最近では、「楔」の翼形をもつプロペラ(写真1)等が開発される等、文字どおり水面下でホットな技術開発が行われています。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Q:長い歴史を持つプロペラですが、どういう点が良いのでしょうか? A:先ず、「プロペラ」という言葉ですが、言語的には推進器を広く一般に指し、外輪や帆等も含まれます。しかし、「スクリュー(らせん)・プロペラ」が船に使われる推進器のほとんどを占めてしまったことから、このスクリュー・プロペラのことを略して一般に、「プロペラ」と呼ぶことが多くなりました。ここでは以後、このスクリュー・プロペラのことを単に「プロペラ」と言います。プロペラは長年の研究成果も加わって、船の推進器としてのエネルギー効率が格段に優れています。 |
|||||||||||||
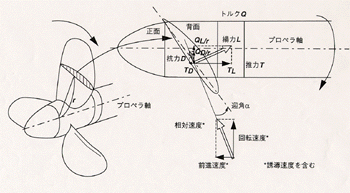 (図-1) プロペラ翼 |
(写真1)「楔」形のプロペラ |
||||||||||||
Q:プロペラの原理を簡単に説明して下さい。 A:プロペラは何枚かのプロペラ翼でできています。プロペラ「翼」というぐらいですから、図-1に示すようにプロペラ翼の断面は飛行の翼と同じです。飛行機はジェットエンジンで前進することで翼の面に垂直な方向の力「揚力」を得て浮かぶことができます。同じようにプロペラは回転することでプロペラの翼の垂直方向の「揚力」を得ます。この揚力の合わさったものが船の推進力になります。もっとも「揚力」の大きさは翼の断面の形や動く速度によって異なります。プロペラは先端ほど早く動きますから、プロペラ翼全体で最も大きな推進力が得られるように翼断面の形を設計すると、スクリューの様なねじれた形になります。 Q:「キャビテーション」とは何でしょうか? A:プロペラの先端の背面ではプロペラ回転が早くなると圧力の非常に低い部分ができます。この部分にもともと水に溶け込んでいる空気が分離して気泡ができることをキャビテーションと言い、船にとっては有害な現象です。できた気泡が圧力の高い所に移動して急激に押しつぶされることで、プロペラの表面に強い衝撃力を与えます。この衝撃力が船に振動を起こしたり、プロペラの表面を凸凹に侵食し、場合によってプロペラを折ってしまう場合もあります。 (写真-3)プロペラにできたキャビテーション
A:船研のプロペラについての長年の研究は、日本ばかりでなく世界に誇れる業績を挙げてきました。昭和30年代には船研の前身である運輸技術研究所において、メーカーと共同で「MAUプロペラ」を開発しました。この開発で作成した設計図表とプロペラ形状オフセットは公表され、造船所等でのプロペラの設計に使われたため、「MAUプロペラ」はその後の日本の商船のほとんどに採用されました。また昭和40年代になるとコンピュータの発達に対応し、船研ではプロペラの性能をコンピュータで計算する理論やプログラムを開発・公表し、現在でも造船所等でプロペラの設計に使われております。昭和50年代からはキャビテーションが大きな問題となり、船研に建設された大型キャビテーション試験水槽で、プロペラの性能試験法とともに、振動・騒音、エロージョン(浸食)等についての計測法の開発を行いました。その後、プロペラに発生するキャビテェーションの形状計測法や実船(実際の船に装備された)プロペラの翼面圧力計測法を世界で初めて開発する等、プロペラの性能や各種の計測法に関して最先端の技術開発を行ってきています。
A:新型プロペラは、トランス・キャビテーティング・プロペラ(TCP)と呼ばれるもので、大型の高速フェリーや高速艇のように、吃水が浅くかつ大馬力で高速巡航する船に用いるもので
A:従来の翼型プロペラの設計技術とSCPの設計手法をうまく組み合わせる等これまでの研究の成果を活用し、新型プロペラの初期設計プログラムと性能解析法の開発を行っています。
A:新型プロペラが実用化されると、フェリー等はより速く、より快適になると共に、燃費が改善できます。その結果、船の運航費の節約に加え、エンジンからの二酸化炭素の排出量等を削減することができ、地球環境の保全に役立つことが期待されます。 |
|||||||||||||
