| ●研究論文(国内の学術雑誌) |
| 1. |
ロータリディスプレーサ形スターリング機関の開発
岩本昭一,平田宏一,戸田富士夫,松尾政弘
日本設計工学会誌, Vol. 28, No. 10, p. 35-40, 1993. |
| 2. |
工業教育のための模型スターリングエンジンの開発と性能試験
浜口和洋,平田宏一,土田三郎,松尾政弘,岩本昭一
日本設計工学会誌, Vol. 31, No. 7, p.259-265, 1996. |
| 3. |
スターリングエンジン再生器用スプリングメッシュマトリックスの基本特性と実機試験
浜口和洋,平田宏一,田村達二
設計工学, 第33巻, 第4号, 1998年4月, 131-137. |
| 4. |
小型発電機用スターリングエンジンの開発に関する基礎研究
(第1報 エンジンの設計・試作並びに性能特性)
平田宏一,香川 澄,山下 巌,岩本昭一
日本機械学会論文集, B編, 第64巻, 621号, 1998年5月, 1600-1607.
 |
小型ポータブル発電装置の動力源を主用途として、出力が100W程度のγ形スターリングエンジンの開発を行った。開発したエンジンは、再生器をディスプレーサピストンに内蔵するとともに、内管が往復動する新型のバヨネット式熱交換器を採用することにより、従来のγ形エンジンと比べて大幅な小型・軽量化を図ることができた。本報では、諸熱損失を考慮した断熱モデル及び多分割モデルを用いてエンジンの設計を行い、解析結果と実験結果とを比較・検討した。その結果、新型の熱交換器は高い伝熱性能を有していること、設計手法は小型エンジンの設計に必要な精度を有していること、を確認した。
|
| 5. |
小型発電機用スターリングエンジンの開発に関する基礎研究
(第2報 シミュレーション計算によるエンジンの性能予測法)
平田宏一,浜口和洋,岩本昭一
日本機械学会論文集, B編, 第64巻, 621号, 1998年5月, 1608-1615.
 |
詳細にエンジンの性能を評価し、エンジン性能の向上策を検討する場合、図示出力のみならず、軸出力も正確に予測する必要がある。本報では、実用的かつ簡易的な小型スターリングエンジンの性能予測法の確立を目的として、クランク室での不可逆的な熱損失及び機械損失を考慮した解析モデルを提案した。そして、解析結果と実験結果とを比較・検討した結果、クランク室での損失は内部の伝熱を考慮することで適切に評価できること、機械損失はクーロン摩擦と粘性摩擦から成り立っており、これによって適切に評価できること、が明らかとなり、本解析モデルは小型エンジンの性能特性を精度よく計算できることを確認した。
|
| 6. |
スターリングエンジンの性能特性
(特に実測値の整理法と性能予測法について)
岩本昭一,平田宏一,戸田富士夫
日本機械学会論文集, B編, 第65巻, 635号, 1999年7月, 2547-2554.
 |
著者らは、スターリングエンジンの出力特性を支配する因子について考察するため、実験結果とシミュレーション計算による計算結果とを比較検討した。本報は、実測値を整理する手法を提案し、これよりスターリングエンジンの一般的な性能特性について検討している。次元解析法により導かれた無次元量を用いて、実測値を整理した結果、設計初期の段階で用いる出力性能を予測する手法が誘導された。この手法は、作動ガスの物性を含めたエンジン仕様から求まる無次元量を導入することによって、作動ガス及び運転条件の相違による影響及びエンジン回転数の予測ができる等の特徴がある。
|
| 6'. |
Performance of Stirling Engines(Arranging Method of Experimental Results and Performance Prediction Method)
IWAMOTO, S., HIRATA, K., TODA, F.
JSME International Journal, Series B, Vol. 44, No. 1, p. 140-147, Feb. 2001.
 |
著者らは、スターリングエンジンの出力特性を支配する因子について考察するため、実験結果とシミュレーション計算による計算結果とを比較検討した。本報は、実測値を整理する手法を提案し、これよりスターリングエンジンの一般的な性能特性について検討している。次元解析法により導かれた無次元量を用いて、実測値を整理した結果、設計初期の段階で用いる出力性能を予測する手法が誘導された。この手法は、作動ガスの物性を含めたエンジン仕様から求まる無次元量を導入することによって、作動ガス及び運転条件の相違による影響及びエンジン回転数の予測ができる等の特徴がある。 |
| 7. |
旅客船内における車いすの走行シミュレーション(駆動力推定用基本モデルの開発)
今里元信,太田 進,平田宏一,宮崎恵子
日本航海学会論文集,105号,2001年9月,p.35-41. |
著者らは、所与の加速度条件下において車いすが安全に走行できるか否かを判定する技術の研究を実施している。実際の船舶において、車いすが安全に走行できるか否かを判定するためには、多くの加速度条件を想定する必要があり、実験だけでは困難であることから、任意の加速度条件下において車いすの走行を模擬できるプログラムを開発中である。本研究の目的は、そのための基礎的なモデルを構築することである。 |
| 8. |
旅客船内における車いすの走行シミュレーション - II. 船内車いす走行軌跡推定モデルの構築 -
今里元信,平田宏一
日本航海学会論文集,109号,2003年9月,p.161-169. |
本報では,船内車いす走行軌跡推定モデルを構築するために,外力加速度と目標位置等からトルクを求める操作モデルを開発し,車いす重心位置の軌跡を導いたことについて述べる。また,船内車いす走行軌跡推定モデルの検証のため、傾斜台における実験および実船実験を実施し,船内等で車いすを走行させた際の計測結果と同一の加速度条件下における計算結果との比較ならびに検討を行う。さらに,船内車いす走行軌跡推定モデルを用いて,動揺下における車いす重心位置の軌跡を推定し,通路の壁に当たる可能性の高い幅を推定する例を示す。 |
| 9. |
Development of Turtle-like Submersible Vehicle
KONNO, A., FURUYA, T., MIZUNO, A., HISHINUMA, K, .HIRATA, K, .KAWADA, M.
Journal of The Japan Institution of Marine Engineering, Vol.41, Special
Issue, p.158-163, Sept. 2006.
|
|
|
|
| ●研究論文(Proceedings) |
| 1. |
STIRLING POWER SYSTEM FOR UNDERWATER APPLICATION
TSUKAHARA, S., KUWABARA, M., HIRATA, K., KUMAKURA, T., ISSHIKI, N.
Proceedings of 6th International Stirling Engine Conference, p. 421-426, 1993. |
| 2. |
DESIGN OF APPLICATIVE 100 W STIRLING ENGINE
KAGAWA, N., HIRATA, K., TAKEUCHI, M., YAMASHITA, I., ARAOKA, K., HAMAGUCHI, K., ISSHIKI, N., MATSUO, M., MATSUSHITA, M., MIYABE, H., MORIYA, S.
Proceedings of the 30th. Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, Book No. 10384C, p. 341-346, 1995. |
A small 100 W displacer type Stirling engine is being developed under a project of a JSME committee, RC127. The project consists of sixteen Japanese academic researchers of universities and governmental laboratories and eleven enterprise members related to the Stirling field. The engine has very unique features. Its expansion cylinder is heated by combustion gas or solar energy directly, and a simple cooling system rejects heat from the working fluid. A regenerator is built in the displacer piston with heating and cooling tubes in which the working fluid flows from/to outer tubes. The outer tubes for heating were located at the top of the expansion cylinder and the tubes for cooling are in the middle of the cylinder.
The target performance is a 100 W output with 20 % thermal efficiency at the operating conditions of 923 K expansion space temperature, 343 K compression space temperature, and 1000 rpm. The 100 W displacer engine was designed based on a design manual established by a related JSME committee, RC110. It contains several guides to design for cycle, heat exchanger system, and mechanism of most Stirling cycle machines. The engine was designed by using the fundamental method, the second- and third-order analyses accomplished with the newly arranged knowledge about each component. This paper presents the engine specifications and the theoretical analysis results. The design method is also introduced briefly.
|
| 3. |
DESIGN OF A 100 W STIRLING ENGINE
KAGAWA, N., HIRATA, K., TAKEUCHI, M., YAMASHITA, I., ARAOKA, K., HAMAGUCHI, K., ISSHIKI, N., MATSUO, M., MATSUSHITA, M., MIYABE, H., MORIYA, S.
Proceedings of 7th International Conference on Stirling Cycle Machines, p. 211-216, 1995. |
A small 100 W displacer type Stirling engine named "Ecoboy-SCM81" is being developed under a project of a JSME committee, RC127. The engine has very unique features. Its expansion cylinder is heated by combustion gas or solar energy directly, and a simple cooling system rejects heat from the working fluid. A regenerator is built in the displacer piston with heating and cooling tubes in which the working fluid flows from/to outer tubes. The outer tubes for heating were located at the top of the expansion cylinder and the tubes for cooling are in the middle of the cylinder.
The 100 W displacer engine was designed based on a design manual established by a related JSME committee, RC110. It contains several guides to design for the cycle, heat exchanger system, and mechanism of most Stirling machines. The engine was designed by using the fundamental method, the second- and third-order analyses combined with the newly arranged knowledge about each components.
This paper presents the engine specifications and its unique components and features.
|
| 4. |
MODEL STIRLING ENGINE WITH VARIABLE PHASE ANGLE MECHANISM
HIRATA, K., TSUKAHARA, S., KUWABARA, M.
Proceedings of 7th International Conference on Stirling Cycle Machines, p. 507-512, 1995. |
| 5. |
THE STIRLING ENGINES FOR TEACHING AND DEVELOP AND PROGRESS OF EDUCATION IN JAPAN
MATSUO, M., HIRATA, K., IWAMOTO, S., TODA, F., ISSHIKI, N.
Proceedings of 7th International Conference on Stirling Cycle Machines, p. 41-46, 1995 . |
| 6. |
STUDIES ON REGENERATIVE ROTARY DISPLACER STIRLING ENGINE
ISSHIKI, N., RAGGI, L., ISSHIKI, S., IWAMOTO, S., MATSUO, M., HIRATA, H.
Proceedings of 7th International Conference on Stirling Cycle Machines, p. 185-190, 1995. |
| 7. |
INVERTED T STIRLING ENGINE (ITSE-1)
TSUKAHARA, S., KUWABARA, M., HIRATA, K., ISSHIKI, N., OHTOMO, M.
Proceedings of 7th International Conference on Stirling Cycle Machines, p. 431-436, 1995. |
| 8. |
TEST RESULTS OF APPLICATIVE 100 W STIRLING ENGINE
HIRATA, K., KAGAWA, N., TAKEUCHI, M., YAMASHITA, I., ISSHIKI, N., HAMAGUCHI, K.
Proceedings of the 31st Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, Book No. vol. 2, p. 1259-1264, 1996.
 |
A small 100 W displacer-type Stirling engine, 'Ecoboy-SCM81' has being developed by a committee of the Japan Society of Mechanical Engineers (JSME). The engine contains unique features, including an expansion cylinder which is heated by either combustion gas or direct solar energy. Also, a simple cooling system rejects heat from the working fluid. A displacer piston has both heating and cooling inner tubes for the working fluid which flows to and from outer tubes. The outer tubes for heating were located at the top of the expansion cylinder and the outer tubes for cooling were located in the middle of the cylinder. A regenerator is located in the displacer piston.
The components of the engine adopted some new technologies. For instance, a porous type matrix consisting of pressed zigzag stainless steel wires was adopted for the regenerator. The matrix is practical for Stirling engines because it can be made at low cost and the assembling process is simplified.
|
| 9. |
REGENERATIVE ROTARY DISPLACER STIRLING ENGINE
ISSHIKI, N., RAGGI, L., ISSHIKI, S., HIRATA, K., WATANABE, H.
Proceedings of the 31st Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, Book No. vol. 2, p. 1249-1254, 1996. |
| 10. |
PERFORMANCE EVALUATION FOR A 100 W STIRLING ENGINE
HIRATA, K., IWAMOTO, S., TODA, F., HAMAGUCHI, K.
Proceedings of 8th International Stirling Engine Conference, p. 19-28, 1997.
 |
A small 100 W displacer-type Stirling engine, Ecoboy-SCM81 has being developed by a committee of the Japan Society of Mechanical Engineers. The engine contains unique features, including an expansion cylinder which is heated by either combustion gas or direct solar energy. Also, a simple cooling system rejects heat from the working gas. A displacer piston has both heating and cooling inner tubes for the working gas which flows to and from outer tubes. A regenerator is located in the displacer piston.
To improve the engine performance efficiently, an analysis model for the prototype engine was developed. The analysis model is based an isothermal method considered a pressure loss in the regenerator, a buffer space loss caused by a leakage of the working gas, and a mechanical loss. In the case of a calculation for the pressure loss, the analysis model adopts a new suggestion that considers effects of entrance and exit area on the velocity distribution in the regenerator. The buffer loss is calculated with three kinds of methods, an isothermal, an adiabatic and a heat transfer model to consider a suitable method for the buffer space model. Some improvement methods for the prototype engine are discussed after the effectiveness of the analysis model is evaluated.
|
| 11. |
COMPARISON OF LOW- AND HIGH TEMPERATURE DIFFERENTIAL STIRLING ENGINES
IWAMOTO, S., TODA, F., HIRATA, K., TAKEUCHI, M., YAMAMOTO, T.
Proceedings of 8th International Stirling Engine Conference, p. 29-38, 1997.
 |
Stirling engines can be operated with various heat sources. We have developed several Stirling engines, included a low temperature differential Stirling engine using hot spring heat and a high temperature differential Stirling engine using a combustion gas as the fuel. These engines have different features and characteristics, and have different thermal performance.
In this paper, the performances of these difference types of Stirling engines were measured, were compared using the normalized values.
|
| 12. |
BASIC CHARACTERISTICS AND APPLIED TESTS OF 'SPRING MESH' AS A NEW REGENERATOR MATRIX FOR STIRLING ENGINE
HAMAGUCHI, K., HIRATA, K., TAMURA, T., ISSHIKI, N.
Proceedings of 8th International Stirling Engine Conference, p. 51-58, 1997. |
| 13. |
EFFECTS OF SUDDEN EXPANSION AND CONTRACTION FLOW ON PRESSURE DROPS IN STIRLING ENGINE REGENERATOR
HAMAGUCHI, K., YAMASHITA, I., HIRATA, K.
Proceedings of the 33rd Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, 1998.
 |
The flow losses in the regenerators greatly influence the performance of the Stirling engine. The losses mainly depend on fluid friction through the regenerator matrix, but are also generated in sudden expansion and contraction flow at the regenerator ends. The latter losses can't be neglected in the case of small area ratio (entrance area/cross-sectional area in regenerator). The pressure drops in regenerators are usually estimated assuming a uniform velocity distribution of working gas in the matrices. The estimation results, however, are generally smaller than practical data. The cross-sectional flow areas of the heater and cooler of typical Stirling engines are smaller than the cross-sectional area of the regenerator. So, it is necessary to understand the quantitative effects of the sudden change in flow area at the regenerator ends on the velocity distribution and pressure drop. In this paper, the effects of the regenerator ends are examined using stacked wire gauzes in the matrix by a steady single blow experiment and presented using the empirical equation defined by effective flow area ratio. The results show that the effective flow area ratio which is an index of the uniformity of the velocity distribution is independent of the mesh number and the Reynolds number but dependent on the entrance and exit areas and the stack thickness. Additionally, the effects of regenerator ends on the pressure drop in an actual engine are studied theoretically and experimentally.
|
| 14. |
Study on Design and Performance Prediction Methods for Miniaturized Stirling Engine
HIRATA, K., IWAMOTO, S.
The 6th Small Engine Technology Conference & Exposion, SAE, p.444-449,
Sept. 1999.
 |
This paper shows a design and performance prediction methods for a miniaturized Stirling engine, in order to develop a small portable generator set. First, a 100 W class Stirling engine is designed and manufactured. In order to miniaturize the engine, unique type heat exchangers were applied. A regenerator was located in a displacer piston. For a piston drive mechanism, a Scotch-yoke mechanism which was useful to realize the small-size engine without any lubricating device, was adopted.
Next, an analysis model for the miniaturized engine is developed to improve the engine performance efficiently. The pressure in the working space is analyzed by an isothermal analysis which takes into account a gas leakage through a piston ring and pressure loss in the heat exchangers. To estimate a shaft power, the mechanical loss and the buffer loss, which is caused by a pressure change in a crank case are considered on the analysis model. The calculated results were compared with the experimental data carefully. Then we suggest how to develop practical Stirling engines as a next step.
|
| 15. |
Study on Turning Performance of a Fish Robot
HIRATA, K., TAKIMOTO, T. and TAMURA, K.
First International Symposium on Aqua Bio-Mechanisms, p.287-292, Aug. 2000.
 |
The aim of this study is to develop a fish mimetic underwater robot with good dynamics performance. At first, we discussed turning modes for the fish robot that uses tail swing. Based on the discussion, the prototype fish robot, which has 340 mm body length, was developed. Just after manufacturing, swimming speed at straight propulsion was measured. Next, we measured turning performance with the suggested turning modes. As the result, it was confirmed that frequency, amplitude and leaning of the tail affect the turning performance. Still more, we made sure that the prototype fish robot turned quickly from straight propulsion and stationary state.
|
| 16. |
Development of a Small 50W Class Stirling Engine
HIRATA, K.
Sixth International Symposium On Marine Engineering, p.235-240, Oct. 2000.
 |
In order to develop a compact and low cost Stirling engine, a gamma type Stirling engine with simple moving-tube-type heat exchangers and a Rhombic mechanism was developed. Its target shaft power is 50 W at engine speed of 4000 rpm and mean pressure of 0.8 MPa using helium as working gas. This paper describes the outline of the engine design and the performance test. The test was done without load, using air in atmospheric condition. Also, a mechanical loss measurement was done in highly pressurized condition, in which the engine was driven by a motor compulsory. Then, methods to get higher performance were considered based on the comparison of experimental and calculated results. The results indicate that a higher performance heat exchanger and decreasing of mechanical loss are needed for the attainment of the target performance.
|
| 17. |
Development of Experimental Fish Robot
HIRATA, K.
Sixth International Symposium On Marine Engineering, p.711-714, Oct. 2000.
 |
Underwater robots are widely used in the fields of ocean development, ocean investigation and marine environmental protection. They need higher efficient of propulsive performance. In order to get an underwater robot with high propulsion efficiency, we have studied on a fishlike swimming mechanism and developed a prototype fish robot. It has about 600 mm body length, and three joints of a tail moved by two servomotors with an original link mechanism. It can simulate various moving patterns optionally. In this paper, experimental results of swimming speed measurements using two types of a tail fin are reported. Also, research areas needed for getting higher performance fish robots are discussed.
|
| 18. |
Acts Toward an Accessible Passenger Boat and Barrier-free Design in Japan
KAMATA, M., MIYAZAKI, K., HIRATA, K., IMASATO, M.
9th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled People, p.598-601, July 2001. |
| 19. |
A Semi Free Piston Stirling Engine for a Fish Robot
HIRATA, K.
Proceedings of 10th International Stirling Engine Conference, p.146-151, Sept. 2001.
 |
In this paper, the author examined to adopt a semi-free-piston Stirling engine (SFPSE) for the power source of a fish robot. One of characteristics of the SFPSE is that the output power can be obtained directly from the reciprocating motion of a power piston. Typical thermal engines convert the reciprocating motion of the piston to rotary motion through a crank mechanism. The rotary motion is suitable for applications such as a screw propeller of a ship. However, in the case of a fish robot, it is the best way that the reciprocating piston drives the oscillating tail fin directly. A great deal of mechanical frictional loss can thus be reduced. This mechanism should result in high potential for efficiency. Two types of experiments were done in this paper. First, the performance of a simple experimental SFPSE - tail fin system was examined experimentally, and it is compared with calculated results based on a simple simulation model. Second, a model boat with a fish-like swimming mechanism driven by a SFPSE was developed. The ship performance was investigated and the adaptability of SFPSE for fish robots was discussed.
|
| 20. |
On aerodynamic characteristics of a hybrid-sail with square soft sail
Toshifumi Fujiwara, Koichi Hirata, Michio Ueno, Tadashi Nimura.
Proceedings of ISOPE 2003. |
| 21. |
On development of high performance sails for a oceangoing sailing ship
Toshifumi Fujiwara, Koichi Hirata, Michio Ueno, Tadashi Nimura.
Proceedings of MARSIM '03. |
| 22. |
On the Characteristics of Walking and Moving by Wheelchair on the Passage of Oscillating Ships
Junko Hayashi, Kuniaki Shoji, Keiko Miyazaki, Koichi Hirata, Aiko Suzuki
Proceedings of 11th Japan Group Meeting on Human Response to Vibration
2003, July 2003. |
| 23. |
Mechanical Loss Reduction of a 100 W Class Stirling Engine
HIRATA, K.
Proceedings of 11th International Stirling Engine Conference, p.338-343,
Nov. 2003.
 |
We have developed a 100 W class displacer-type Stirling engine named 'Ecoboy-SCM81' since 1995. The original engine has a mechanical seal as an external seal device. On the other hand, a hermetic Stirling engine, which has a generator in a pressurized crankcase, is suitable for an application of a generator set. Because the hermetic engine does not have any external seal device between the working space and the atmosphere, and it expects to have small mechanical loss. Then we remodel the original Stirling engine to the hermetic structure. Also, in order to reduce the mechanical loss, the shot peening of molybdenum-disulfuride, which is one of the surface treatments, is applied to the cylinder wall, a surface of the displacer rod and other mechanical parts. And, the performance of the engine is measured for a comparison with that of the original engine. As the result, it is confirmed that the hermetic engine has higher shaft power and generator power than that of the original engine. |
| 24. |
Evacuation Simulation for Disabled People in Passenger Ship
Keiko Miyazaki, Mitujiro Katsuhara, Hiroshi Matsukura, Koichi Hirata, TRANSED
2004, May 2004. |
| 25. |
Development of a Multi-cylinder Stirling Engine
Koichi Hirata, Masakuni Kawada
Proceedings of 12th International Stirling Engine Conference, p.315-324, Sept. 2005.
 |
We have researched a multi-cylinder Stirling engine for a waste heat recovery
system. The multi-cylinder Stirling engine has a possibility to achieve
higher efficiency than a single-cylinder engine. In this paper, we discuss
a simple thermal analysis for the multi-cylinder engine. And based on the
analyzed result, a prototype engine is designed and built in our laboratory.
The prototype engine consists of three engine units that have different
piston stroke for each unit to getting the optimal thermal condition. Also
it has unique components, such as a heater made from a block of aluminum
alloy and an assembling cooler. As the result of the previous operating
test, it is confirmed that the shaft power of the prototype engine is bigger
than the sum of shaft power of each engine units. |
| 26. |
Discussion of Applicative Marine Stirling Engine Systems
Koichi Hirata, Masakuni Kawada
7th International Symposium On Marine Engineering, Oct. 2005.
 |
Many kinds of internal combustion engines are used as a prime mover of traffic systems. Also the electric power systems, such as fuel cells, an electric propulsive ship and an electric automobile, are developed for the environmental preservation. On the other hand, a Stirling engine, which is an external engine, has excellent characteristics, which are a high thermal efficiency, multi-fuel capability and low pollution. In this paper, we discuss about marine applications using the Stirling engine. They are a prime mover for a large ship, a hybrid system for a small vehicle and waste heat recovery systems with a marine Diesel engine. We also consider the technical problems of the marine Stirling engine systems. |
| 27. |
Design of an Experimental Manta-like Underwater Robot
Kazuhisa Hishinuma, Akihisa Konno, Akisato Mizuno, Koichi Hirata, Masakuni
Kawada
7th International Symposium On Marine Engineering, Oct. 2005. |
| 28. |
Development of Turtle-like Submergence Vehicle
Akihisa Konno,Takuro Furuya, Kazuhisa Hishinuma, Akisato Mizuno, Koichi
Hirata, Masakuni Kawada
7th International Symposium On Marine Engineering, Oct. 2005. |
| 29. |
A Support System for Flexible Arrangements of Escape Routes on Passenger
Ships
Keiko Miyazaki, Koichi Hirata
7th International Symposium On Marine Engineering, Oct. 2005. |
| 30. |
Development and performance estimation of flapping fin propulsion system
Akihisa Konno, Koichi Hirata, Masakuni Kawada
ISABMEC, July 2006 |
|
|
|
| ●著書 |
| 1. |
模型スターリングエンジン
岩本昭一,浜口和洋,平田宏一,松尾政弘,戸田富士夫
山海堂, 1997年4月
 ●関連ページへ ●関連ページへ |
本書は、模型スタ−リングエンジンを設計・製作するためのマニュアルであり、これからスタ−リングエンジンを学ぼうとする人達のための入門書であります。スタ−リングエンジンの基礎理論と設計・製作するための手法、すなわち「理論と実際」の基礎が一通り述べられていますので、入門書としては最適な著書である、と自負しております。(「まえがき」より) |
| 2. |
スターリングエンジンの理論と設計
山下 巌,浜口和洋,香川 澄,平田宏一,百瀬 豊
山海堂, 1999年7月
 ●関連ページへ ●関連ページへ |
本書は,スターリングエンジンの基礎理論,熱力学的解析手法や内外の開発状況はもちろん,熱交換器,シール,出力取出し機構などの構成要素についてもできる限り詳細に記述することにより,スターリングエンジンに対する基礎知識とその設計手法を提供することを目的として著わされました。特に,設計手法については,できる限り具体例を示すように留意しましたが,高度なスターリングエンジンを設計しようとすると,むろんこれだけでは不十分でしょう。その場合には,挙げられている参考文献,資料としてCD-ROMとともに提供されている設計例や内外情報の収集方法が役立つものと思われます。
|
| 3. |
スターリングエンジン製作マニュアル
松尾政弘:編,岸 教男,小林義行,土田三郎,平尾尚武,平田宏一,神原 将,ナカマシゲトモ
誠文堂新光社 , 2001年9月 |
本書は、スターリングエンジンを自作するための入門書として位置付け、特別な工作機械や材料を使わずに手加工で自作できるエンジンの作り方や、旋盤などを使った本格的な工作、そして作動原理と各種模型エンジンの活用例について紹介し、併せてこのスターリングエンジンの未来の夢について記述した。
|
| 4. |
はじめて学ぶ熱力学
斎藤孝基,濱口和洋,平田宏一
オーム社 , 2002年3月 |
若い人たちには漫画も大事な文化である。絵を楽しみながら読むことができる漫画とまではいかなくても教科書にも一目で分かるような配慮が必要なので、図や表を多くし、なるべく図表の中に説明文を加えるようにした。エンタルピにしろエントロピにしろ、厳密に定義を導くことよりも、先ず慣れてもらうことを念頭においた。【まえがきより抜粋。】
|
| 5. |
機械学ポケットブック
機械学ポケットブック編集委員会/編.
オーム社,2004年12月 |
熱機関(エンジン)とは,熱エネルギーを利用して動力や電気を取り出す機械である。すなわち,燃料を補給していれば連続した運転を実現でき,自動車や船舶,航空機などの輸送機械や火力発電所,原子力発電所などで利用されている。本章では,様々な形式の熱機関の基本メカニズムについて学び,エネルギーの有効利用と環境保全について考える。【執筆担当「熱機関」より一部を抜粋】 |
| 6. |
マイコン搭載ロボット製作入門(AVRで魚型ロボットのメカを動かす)
平田宏一
CQ出版,2005年12月
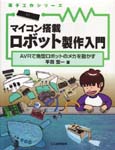 ●出版社の関連ページへ ●出版社の関連ページへ |
自分の手でモノを作るのはとても楽しいことです。それも自分の思い通りに動くものであればなおさらのことです。本書では,マイコンを使った簡単な電子回路を製作し,様々なモータを動かしています。そして,その動きを利用して,魚のように泳ぐロボットを製作します。マイコンを使ってモータを動かすことができれば,魚ロボットばかりでなく,様々な電子機械に応用できるのは言うまでもありません。「モノ作り」の楽しさは,各自のアイデアを具現化することにあります。読者の方々には,本書で紹介するマイコンの知識をはじめの題材として,新たなモノ作りへと発展させていただきたいと考えています。【まえがきより抜粋。】 |
| 7. |
絵とき 機械加工の基礎のきそ
平田宏一
日刊工業新聞社,2006年1月
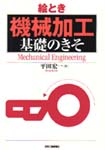 ●出版社のページへ ●出版社のページへ |
筆者は,数年前より機械工学科の大学生を研究室に受け入れ,卒業研究の指導をしています。学生たちには,主として研究・実験装置開発の課題を与え,その装置のほとんどを学生と筆者の「手作り」で製作しています。そのようなことから,学生や若い技術者が最初に眺める機械加工のインターネット資料を作り始めました。本書は,その資料を取りまとめて,執筆されたものです。【まえがきより抜粋。】 |
| 8. |
絵とき 機械設計の基礎のきそ
平田宏一
日刊工業新聞社,2006年3月
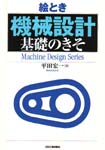 ●出版社のページへ ●出版社のページへ |
これまでに,筆者は小型スターリングエンジンや魚ロボット,バリアフリー機器などの様々な実験装置の設計・試作をしてきました。それらの全ては単品製作であり,工業製品として市販されているような量産品ではありません。そして,ほとんどの部品を自分の手で製作しているため,製作性(=作りやすさ)を考えて設計することがほとんどです。また,実験装置であるため,製作コストを考える必要がありません。一般の機械材料としてよく使われている炭素鋼を使うことはほとんどなく,溶接構造とすることもほとんどありません。そのようなことから,本書で紹介する「機械設計」は,一般に使われている「機械設計」の教科書とは異なる点が多くあります。【まえがきより抜粋。】 |
| 9. |
絵とき 機械用語事典 作業編
平田宏一,大高敏男,川田正國
日刊工業新聞社,2007年1月
●出版社のページへ |
本書は,若い機械技術者を対象にして,実際の作業現場で使われる機械用語をまとめています。約360の機械用語を3人の著者で分担して執筆しています。それぞれの用語は,機械工作,溶接・ろう付け,手工具・手仕上げ,材料,計測,その他の6つに大きく分類されています(大分類)。さらに,それらを用途や種類別に細かく分類し(中分類),関連性の高い用語を順番に並べています。【まえがきより抜粋】 |
| 10. |
絵とき 機械用語事典 設計編
平田宏一,大高敏男,川田正國
日刊工業新聞社,2007年5月
●出版社のページへ |
今から数ヶ月前,筆者らは若い機械技術者を対象にして「絵とき 機械用語事典
作業編」をまとめ,機械加工や組立の現場で飛び交う専門用語を解説しました。作業編では,主として年輩の方と若者が適切なコミュニケーションをとるために,正しく用語を理解しなくてはいけないという発想で執筆を進めました。本書「設計編」は,その続編として,機械の設計を進める際に使われる用語をまとめています。本書も同様に,技術者同士がそれぞれの用語を正しく理解し,適切なコミュニケーションをとるための知識をまとめるように心がけました。【まえがきより抜粋】 |
|
|
|
| ●解説,資料 |
| 1. |
模型スターリングエンジンを教材とした実践的設計教育(技術資料)
浜口和洋,佐賀直次,植木正則,林 耕平,平田宏一
日本設計工学会誌, Vol. 29, No.11, p. 30-35, 1994. |
| 2. |
模型スターリングボート(解説)
平田宏一
日本舶用機関学会誌, Vol. 30, No.8, p.597-599, 1995. |
| 3. |
スターリング機器におけるトライボロジー(解説)
岩本昭一,川田正國,戸田富士夫,平田宏一
日本舶用機関学会誌, Vol. 33, No. 8, 1998. |
スターリングサイクルエンジン及び冷凍機の研究開発の歴史は長く,これまで多くの開発実績を有している.さらには解析手法の高度化によって,実機の高性能化と高効率化を実現している.しかしながら,実用化を目指すにはさらに寿命特性と信頼性の向上を図ることが必要な条件であり,それを実証することが開発課題として残されている.
スターリングサイクル機器におけるトライボロジの問題は複雑で多岐にわたる.したがって,ここでは筆者らがこれまでに試作開発したエンジンあるいは冷凍機を例として,そこに採用したシール方式や潤滑方式の特徴とその構造について紹介する. |
| 4. |
スターリングエンジンを作ろう
(1) 動作原理と開発の歴史(解説)
浜口和洋,平田宏一
エンジンテクノロジー, Vol.1, No,1, p.73-79, 山海堂, 1999年3月. |
スターリングエンジンの歴史と原理、そして工作機械を用いずに簡単に製作することができる模型エンジンを紹介する。 |
| 5. |
スターリングエンジンを作ろう
(2) 設計・製作編(解説)
平田宏一,浜口和洋
エンジンテクノロジー, Vol.1, No,2, p.64-71, 山海堂, 1999年5月. |
模型スターリングエンジンには、運転することを目的としたエンジン、熱力学的サイクルを模擬するエンジン、高回転を達成する模型エンジン、さらに実用エンジンに近い高性能なエンジンまで様々である。本稿では、いくつかの模型エンジンを紹介し、模型エンジンの出力向上方法、実際に模型自動車や発電機の動力源として出力を取り出す方法、さらに設計・製作時の注意事項について解説する。
|
| 6. |
スターリングエンジンを作ろう
(3) 出力測定編(解説)
平田宏一,浜口和洋
エンジンテクノロジー, Vol.1, No,3, p.72-77, 山海堂, 1999年7月. |
設計・試作したエンジンの性能向上並びに性能評価を行う場合,出力測定は必要不可欠である。本稿では,出力や熱量についての基礎知識を概説するとともに,出力測定法について解説する。あわせて,詳細な性能測定が可能で,かつ自作可能な実験用スターリングエンジンを紹介する。
|
| 7. |
スターリングエンジンを作ろう
(4) 工学教育と将来性(解説)
浜口和洋,平田宏一
エンジンテクノロジー, Vol.1, No,4, p.70-75, 山海堂, 1999年9月. |
| 8. |
海上技術安全研究所における魚ロボットの研究
平田宏一
設計工学,Vol.38,No.6,p.293-301,2003年6月.
 |
著者らは,高い遊泳性能を有する海中作業ロボットの開発並びに新しい船舶用高性能推進装置の開発を目指して,魚の泳法を模擬したロボット(魚ロボット)の研究を進めてきた。本報では,魚ロボットの推進方法や運動性能について概説する.そして,著者らが現在までに開発してきた魚ロボットの構造や性能について解説する。 |
| 9. |
スターリングエンジンの原理と開発事例
平田宏一,川田正國
機械の研究,第56巻第9号,p.941-949,2004年9月.
 |
本報では,スターリングエンジンを理解するための導入として,本エンジンの基本原理,形式並びに開発事例について解説する。 |
| 10. |
機関に係わる新しい技術課題(5)−エネルギーの有効利用技術とスターリング機関−
平田宏一,海技通信,2004年9月号,No.640,p.2,2004年9月.
 |
交通機関の動力源としては,小型乗用車では小型・軽量なガソリン機関,航空機では大推進力が得られるジェット機関,そして船舶の主機関としては高効率なディーゼル機関が主流である。今回は,ディーゼル機関よりも古くに発明され,発展と低迷を繰り返しながら開発が進められてきたスターリング機関について述べ,エネルギーの有効利用技術について考える。 |
| 11. |
船と海のスターリングエンジン
平田宏一,船と海のサイエンス,Vol.10,2004秋期号,p.57-59,2004年9月.
 |
本稿で述べるスターリングエンジンは,ディーゼルエンジンよりも古くに発明され,発展と低迷を繰り返しながら開発が進められてきた外燃機関である。以下,低公害性・燃料の多様性など,環境調和性に優れた特徴を持つスターリングエンジンが,どのような船舶分野に適用できるのか考えてみたい。 |
| 12. |
加工しにくい設計、加工しやすい設計を理解する!
平田宏一
機械設計,日刊工業新聞社,Vol.49,No.10(2005年8月号),p.18-27,2005年7月.
 |
最近のモノづくりの現場は分業化が進んでいる。設計者は設計だけを行い,加工者は加工に専念する。場合によっては,設計者と製図者(CADオペレーター)とが分業されていることもある。一方,筆者は自分自身が使う実験装置を,設計から加工まで自らの手で行うことが多い。本稿は,その経験から得た知見をまとめたものであり,入社1〜2年程度の新人設計者を対象に「加工を考えた設計」について解説している。 |
| 13. |
スターリングエンジン発電機
平田宏一
日本機械学会誌,Vol.108,No.1045,p.46-47.2005年12月
 |
18世紀に発明されたスターリングエンジンは,発展と低迷を繰り返しながら,研究・開発が進められている外燃機関である。このエンジンは,高熱効率性,燃料の多様性,低公害性といった優れた特徴がある。そのため,省エネルギーや環境問題が深刻な社会問題となっている現在,スターリングエンジンへの期待が高まってきている。以下,スターリングエンジンの概要と開発状況について解説する。 |
| 14. |
スターリングエンジンの研究・開発動向
平田宏一
(財)エネルギー総合工学研究所,2006年4月
 |
本報では,当研究所で進めている排熱利用スターリングエンジンに関連した研究をはじめ,国内外で研究・開発が進められている高性能スターリングエンジンの現状,バイオマスや太陽熱を利用した関連研究について解説する。 |
| 15. |
ものづくりを始めよう!
第1回 ものづくりの楽しみ方
平田宏一
機械設計,日刊工業新聞社,Vol.55,No.1(2007年1月号),p.50-54,2006年12月. |
本連載におけるものづくりは,自らがアイデアを創出し,設計・製図を行い,部品を加工し,機械を組み立て,さらにはその評価試験をするまでの広い範囲を総称して考えていく。第1回では,ものづくりの要点と楽しさを考えてみる。そして,次回以降,筆者らが研究開発しているスターリングエンジンや水中ロボットなどのものづくり事例を紹介しながら,より具体的なものづくりについて考えてみたい。 |
| 16. |
ものづくりを始めよう!
第2回 ものづくり事例 〜模型スターリングエンジン編〜
平田宏一
機械設計,日刊工業新聞社,Vol.55,No.2(2007年2月号),p.86-91,2007年1月. |
ものづくり事例の一つとして,筆者らが研究・開発を進めているスターリングエンジンを紹介する。発想を具現化することや作りやすさを考える模型スターリングエンジンと出力性能や熱効率が重要視される高性能スターリングエンジンは,開発コンセプトをはじめ,ものづくりの考え方がかなり異なっている。本報では,スターリングエンジンの構造や特徴を解説した後,ものづくりの観点から模型スターリングエンジンについて考えてみる。 |
| 17. |
ものづくりを始めよう!
第3回 ものづくり事例 〜高性能スターリングエンジン編〜
平田宏一
機械設計,日刊工業新聞社,Vol.55,No.3(2007年3月号),p.72-77,2007年2月. |
今回は,実用化を目指した高性能スターリングエンジンのものづくり事例を紹介する。前回の記事で述べた通り,発想を具現化することや作りやすさを考える模型スターリングエンジンと出力性能や熱効率を重視する高性能スターリングエンジンとでは,開発コンセプトをはじめ,ものづくりの考え方がかなり異なっている。以下,スターリングエンジンの高性能化の手法について簡単に解説した後,筆者らが研究・開発を進めている排熱利用スターリングエンジンを紹介しながら,ものづくりの要点を考えてみる。 |
| 18. |
ものづくりを始めよう!
第4回 ものづくり事例 〜魚ロボット・基本編〜
平田宏一
機械設計,日刊工業新聞社,Vol.55,No.4(2007年4月号),p.62-97,2007年3月. |
今回と次回の記事では2回に渡って,筆者らが研究・開発を進めている魚の泳法を模擬したロボット(魚ロボット)のものづくり事例を紹介していく。魚ロボットの研究・開発は,高い遊泳性能を有する海中作業ロボットの開発を目指して行われている。高性能で実用的な魚ロボットを開発できれば,船舶への適用や海洋調査,生態観測などに活用できると考えている。
|
| 19. |
ものづくりを始めよう!
第5回 ものづくり事例 〜魚ロボット・応用編〜
平田宏一
機械設計,日刊工業新聞社,Vol.55,No.5(2007年5月号),p.69-74,2007年4月. |
今回は,魚ロボットのいくつかの応用例を紹介する。さらに,当研究室の研修生が実際に魚ロボットの設計・製作を行った事例を簡単に紹介し,ものづくり教育について考えてみたい。 |
|
|
|
|
|
|
| ●講演発表(口頭発表) |
| 1. |
スターリングエンジンの動特性に関する研究(スターリングエンジンの3形式とその比較)
戸田富士夫, 岩本昭一, 平田宏一, 松尾政弘
第46回日本舶用機関学会学術講演会(1990年5月). |
| 2. |
ロータリディスプレーサ型スターリングエンジンの試作
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 松尾政弘
日本設計工学会関西支部平成2年度研究発表講演会要旨集(1990年10月). |
| 3. |
ロータリディスプレーサ形スターリングエンジンの設計・試作
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 吉川礼司, 松尾政弘
第47回日本舶用機関学会学術講演会(1991年5月). |
| 4. |
極低温度差スターリングエンジンの設計・試作
岩本昭一, 戸田富士夫, 伊藤進一, 平田宏一, 松尾政弘
第47回日本舶用機関学会学術講演会(1991年5月). |
| 5. |
スターリングエンジンの動特性に関する研究
岩本昭一, 戸田富士夫, 松尾政弘, 平田宏一
第49回日本舶用機関学会学術講演会(1992年5月). |
| 6. |
教材用スターリングエンジンの設計・試作
平田宏一, 岩本昭一, 戸田富士夫, 松尾政弘
日本設計工学会講演論文集, No.92-秋期(1992年10月). |
| 7. |
極低温度差スターリングエンジンの展望
平田宏一, 岩本昭一, 戸田富士夫, 松尾政弘
日本設計工学会東北支部講演論文集(1992年11月). |
| 8. |
日本における教材用スターリングエンジンの進展について
松尾政弘,平田宏一,岩本昭一,戸田富士夫,一色尚次
日本設計工学会講演論文集,No.96-春期,p.17-19,(1996年5月). |
| 9. |
100 W級スターリングエンジンの性能解析
平田宏一, 香川澄, 竹内誠, 山下巌, 浜口和洋, 一色尚次, 岩本昭一
日本機械学会第74期全国大会講演論文集(1996年9月).
 |
1994年、日本機械学会RC110研究分科会においてスターリングエンジンの設計手法が構築され、研究成果報告書が作成された。同学会RC127研究分科会(1994〜1996)では、RC110研究分科会において構築された設計手法の検証・確立を目的として、その設計手法に基づき100W級スターリングエンジン「Ecoboy-SCM81」の設計・試作を行った。本報では試作エンジンの構造及び性能特性について記す。
|
| 10. |
低温度差スターリングエンジンの性能解析(メカニズム効率の挙動)
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一
日本機械学会第74期全国大会講演論文集(1996年9月). |
| 11. |
低温度差スターリングエンジンの性能解析(流動抵抗を考慮した図示出力の解析解)
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一
日本機械学会第74期全国大会講演論文集(1996年9月). |
| 12. |
一方向性軸シール装置の性能特性
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一
第58回日本舶用機関学会学術講演会(1997年5月). |
| 13. |
スターリングエンジンの性能解析(メカニズム効率の挙動)
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 角田孝一
第58回日本舶用機関学会学術講演会(1997年5月). |
| 14. |
低温度差スターリングエンジンの性能解析(メカニズム効率を用いた性能予測法)
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 山本格, 竹内誠
第58回日本舶用機関学会学術講演会(1997年5月). |
| 15. |
低温度差ソーラースターリングエンジンの性能特性
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 古茂田潮
日本設計工学会講演論文集, No.97-春期(1997年5月). |
| 16. |
排気ガスを熱源とするスターリングエンジンに関する研究
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 上杉宏, 大内宣利
日本設計工学会講演論文集, No.97-春期(1997年5月). |
| 17. |
1 kW級低温度差スターリングエンジンの設計・試作
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 竹内誠
日本機械学会第7回環境工学総合シンポジウム'97講演論文集(1997年7月). |
| 18. |
300 W級低温度差スターリングエンジンの性能特性
戸田富士夫, 岩本昭一, 平田宏一, 山本格, 竹内誠
日本機械学会第7回環境工学総合シンポジウム'97講演論文集(1997年7月). |
| 19. |
火花点火機関の性能解析
戸田富士夫, 岩本昭一, 平田宏一, 金永星, 針谷安男, 菅野知美
日本機械学会第14回内燃機関シンポジウム講演論文集(1997年9月). |
| 20. |
発電用小型スターリングエンジンの性能解析
平田宏一, 岩本昭一, 戸田富士夫
日本機械学会第1回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集(1997年10月).
 |
本報では、実用的かつ簡易的な性能予測法の確立を目的として、バッファ損失及び機械損失を考慮した解析モデルを提案する。そして、解析モデルによる計算結果と実機による実験結果とを比較・検討し、本解析モデルの妥当性について考察する。
|
| 21. |
1 kW級低温度差スターリングエンジンの性能特性
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 竹内誠
日本機械学会第1回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集(1997年10月). |
| 22. |
低温度差スターリングエンジンの性能解析(簡易ガス温度推定法)
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一
日本機械学会第1回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集(1997年10月). |
| 23. |
教材用スターリングエンジンに関する一考察
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 古茂田潮
日本機械学会第1回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集(1997年10月). |
| 24. |
低温度差スターリングエンジンの性能予測並びに設計手法に関する研究
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 古茂田潮
日本舶用機関学会第60回学術講演会(1998年5月). |
| 25. |
スターリングエンジンの性能解析(特にメカニズム効率について)
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 角田孝一
日本舶用機関学会第60回学術講演会(1998年5月). |
| 26. |
低温度差スターリングエンジンの性能解析
岩本昭一, 戸田富士夫, 平田宏一, 大内宣利
日本舶用機関学会第60回学術講演会(1998年5月). |
| 27. |
スターリングエンジンの最新研究とトライボロジの課題
岩本昭一, 川田正國, 戸田富士夫, 平田宏一
日本機械学会ブロック合同講演会-'98浦和-講演論文集(1998年9月). |
| 28. |
スターリングエンジンの簡易性能予測法
平田宏一, 岩本昭一, 戸田富士夫
日本機械学会第2回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集(1998年10月).
 |
著者らは、スターリングエンジンの出力特性を支配する因子について考察するため、実験結果とシミュレーション計算による計算結果とを比較検討した。本報は、実測値を整理する手法を提案し、これよりスターリングエンジンの一般的な性能特性について検討している。次元解析法により導かれた無次元量を用いて、実測値を整理した結果、設計初期の段階で用いる出力性能を予測する手法が誘導された。 |
| 29. |
スターリングエンジンのシール性能について
平田宏一
日本機械学会第2回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集(1998年10月).
 |
スターリングエンジンにおいて、ディスプレーサのピストンリングは、他のシール装置と比べて、作動部の温度が高く、その耐久性が問題となるため、そのガス漏れ特性がエンジン性能に及ぼす影響を詳細に調べる必要がある。本報では、100 W級エンジンを用いて、ディスプレーサにおけるピストンリングのガス漏れ特性がエンジン性能に及ぼす影響について実験的検討を行った。 |
| 30. |
相似則によるスターリングエンジン熱交換器の設計手法
浜口和洋, 山下巌, 平田宏一
日本機械学会第2回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集(1998年10月). |
| 31. |
50W級小型スターリングエンジンの設計・試作
平田宏一
日本舶用機関学会第62回学術講演会, p.53-56,(1999年5月).
 |
スターリングエンジンの実用化を阻む問題点として、多数の伝熱管を溶接して製作される熱交換器の製造コストが高いこと及びエンジン重量当たりの出力が小さいことがあげられる。本報では、それらの解決策を見出すことを目的とし、簡略化した熱交換器を採用した実験用小型スターリングエンジンの設計・試作を行う。
|
| 32. |
小型魚ロボットの設計・試作
平田宏一
日本設計工学会平成11年度春期研究発表講演会講演論文集, No.99−春季, p.29-32, (1999年5月).
 |
本研究は,船舶や潜水船の高効率推進装置の開発,そして周囲の状況に応じて自らが最適な泳法を学んでいく知能ロボットの開発を目的としている.本報では,魚ロボットの基本的な推進特性を調べるために設計・試作した,全長190
mm程度の小型魚ロボットの基本的な特性について記す. |
| 33. |
魚ロボットに関する研究
平田宏一, 春海一佳, 田村兼吉, 児玉良明, 冨田宏, 牧野雅彦
平成11年度(第73回)船舶技術研究所研究発表会講演集, p.190-193(1999年6月).
 |
魚のように海中を自由に泳ぎ回り、しかも高効率で機敏な旋回性能を有する魚ロボットが開発されれば、海中調査や生態観測に多いに貢献するであろう。本報では、魚ロボットの基本的な推進特性を調べるために設計・試作した、全長190
mm程度の模型魚ロボットの基本的な特性を中心に解説する。 |
| 34. |
50 W小型スターリングエンジンの性能特性(その1,大気圧空気における運転試験結果並びに機械損失の測定)
平田宏一, 吉田誠, 山下巌
日本機械学会第3回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.49-52(1999年10月).
 |
スターリングエンジンの実用化を阻む問題点として,熱交換器の製造コストが高いこと及びエンジン重量当たりの出力が小さいことがあげられる。本報では,それらの解決策を見出すために試作した実験用スターリングエンジンについて概説し,試作直後の大気圧空気における運転試験結果並びに実機による機械損失の測定結果について述べる。 |
| 35. |
魚ロボットに用いるセミフリーピストン形スターリングエンジン
平田宏一, 植木原明, 山下巌
日本機械学会第3回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.78-79(1999年10月).
 |
本研究は,推進特性,旋回特性及び運動制御といった魚ロボットの基本特性を評価し,さらに魚ロボットに用いる最適な動力源を検討することを目的としている。本報では,魚ロボット並びにセミフリーピストン形スターリングエンジンの構造及び特徴について概説し,本エンジンの魚ロボットへの適用性について検討する。
|
| 36. |
様々な熱機関サイクルで運転可能な外燃式機関
汐崎浩毅, 平田宏一
日本機械学会第3回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.91-82(1999年10月). |
| 37. |
実験用魚ロボットの旋回性能に関する研究
平田宏一, 藁科真一
日本設計工学会東北支部,平成11年度研究発表講演会,p.68-71(1999年11月).
 |
本報では,魚ロボットの旋回方法について検討した後,主として旋回性能に着目した実験用魚ロボットの設計・試作を行い,基本的な運動形式における旋回性能を測定した.
|
| 38. |
ファジィ理論を利用した魚ロボットの運動制御
平田宏一, 春海一佳
日本設計工学会東北支部,平成11年度研究発表講演会,p.72-75(1999年11月).
 |
魚ロボットの運動形式は複雑かつ多様であり,従来の工学的制御手法で最適な運動形式を模索するのは極めて難しい。本報では,研究の第一段階として,魚ロボットの直進運動に着目し,ファジィ理論を利用した魚ロボットの運動制御法を提案する。さらに,簡易的なシミュレーション計算によってその適用性について考察する。 |
| 39. |
実験用魚ロボットの性能特性
平田宏一
第7回アクアバイオメカニズム研究会講演集,(2000年3月).
 |
海中技術は,海洋開発や海洋環境保全において極めて重要であり,そのような観点から,海中ロボットの開発が盛んに行われている。本報では,設計・試作した2種類の実験用魚ロボットを紹介し,尾ひれの形状や運動パターンが運動性能に及ぼす影響について概説する。
|
| 40. |
実験用魚ロボットの推進性能
平田宏一
日本設計工学会平成12年度春期研究発表講演会講演論文集, p.163-166, (2000年5月).
 |
魚の泳法を模擬した海中ロボットは高効率推進が可能であると考えられる。本報では,全長600mmの実験用魚ロボットを設計・試作し,尾ひれの形状や運動パターンが推進性能に及ぼす影響を測定する。
|
| 41. |
実験用セミフリーピストン形スターリングエンジンの性能特性
平田宏一
日本舶用機関学会,第64回マリンエンジニアリング講演論文集, p.105-108,(2000年5月).
 |
セミフリーピストン形スターリングエンジンはクランク機構を持たないため,機械損失の大幅な低減が可能であり,ロボットのアクチュエータのような往復運動を利用する機器に適していると考えられる。本報では,セミフリーピストン形エンジンの性能解析を行い,実験用エンジンの実験結果と比較・検討する。
|
| 42. |
魚ロボットに関する研究(その2 実験用魚ロボットの開発と今後の課題)
平田宏一, 春海一佳, 滝本忠教,児玉良明, 冨田宏, 牧野雅彦, 田村兼吉, 劉 浩
平成12年度(第74回)船舶技術研究所研究発表会講演集,p.213-216,(2000年6月).
 |
本研究は,推進と抵抗の発生メカニズムが相互に干渉しあう「自己推進運動体」(例えば魚)について研究を行い,エネルギを最小とする新しい推進方法の可能性についての基礎的な知見を得ることを主目的としている。本報では,自己推進運動体による推進の実験ツールとして開発した魚の泳ぎを模擬するロボットについて概説する。
|
| 43. |
推進性能実験用魚ロボットの基本性能
平田宏一,滝本忠教,牧野雅彦
平成12年度(第74回)船舶技術研究所研究発表会講演集,p.231-232,(2000年6月).
 |
本研究では,魚ロボットの詳細な推進性能を測定することを目的とし,全長600mmの実験用魚ロボットの設計・試作した。本実験用魚ロボットは,加速性に優れたニジマスから高速・高効率なマグロまで,様々な運動パターンが模擬できることを設計指針としている。 |
| 44. |
旋回性能実験用魚ロボットの基本性能
平田宏一,滝本忠教
平成12年度(第74回)船舶技術研究所研究発表会講演集,p.233-234,(2000年6月).
 |
魚ロボットが実際の魚と同等の加速性能や旋回性能を実現できれば,海中ロボットとしての実用価値が高められるものと考えられる。本報では,魚ロボットの旋回方法について検討した後,開発した旋回性能に着目した実験用魚ロボットについて概説し,基本的な運動パターンにおける旋回性能の測定結果について述べる。 |
| 45. |
魚ロボットに用いるスターリングエンジンに関する研究
平田宏一
平成12年度(第74回)船舶技術研究所研究発表会講演集,p.235-236,(2000年6月).
 |
従来から開発されている海中ロボットは,一般に蓄電池を用いた電気モータを動力源としているが,蓄電池はエネルギ密度が低く長時間の航行は困難である。本報では,ピストンの往復運動を直接動力として利用できる,セミフリーピストン形スターリングエンジンの魚ロボットへの適用性について考察する。 |
| 46. |
50 W小型スターリングエンジンの性能特性(その2,発電機のハーメティック化とその運転結果)
平田宏一,小宮一郎,山下巌
日本機械学会第4回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.23-26(2000年10月).
 |
著者らは,低コスト化・小型化を目指して,目標出力が50 Wの実験用小型スターリングエンジンの開発を進めている。本報では,実験用小型スターリングエンジンの機械損失を低減するため,発電機をクランクケースと連結した圧力容器に内蔵した。さらに,作動ガスにヘリウムと窒素を使用し,エンジン性能を測定した。
|
| 47. |
セミフリーピストン形スターリングエンジンを用いた魚ロボットの開発
平田宏一,小宮一郎,杉浦忠,山下巌
日本機械学会第4回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.93-94(2000年10月).
 |
本報では,大気圧空気で作動するセミフリーピストン形エンジンを試作し,これを魚の推進方法を利用した模型ボートに搭載し,運転試験を行った。その結果,試作エンジンは魚の推進方法を模擬した推進装置により推進力を発生し,非常に低速ではあるが力強く推進することを確認できた。
|
| 48. |
水素内燃スターリングエンジンの燃焼実験
森田浩之,渋谷嘉人,高橋三餘,倉田修,山下巌,平田宏一
日本機械学会第4回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.63-66(2000年10月). |
| 49. |
魚ロボットの抵抗測定と流体力学的検討
瀧本忠教,平田宏一,牧野雅彦
日本設計工学会東北支部,平成12年度研究発表講演会,p.84-87(2000年10月). |
| 50. |
旅客船内での車いす利用に関する研究
今里元信,宮崎恵子,平田宏一
日本設計工学会東北支部,平成12年度研究発表講演会,p.48-49(2000年10月).
 |
| 51. |
高速化を目指した実験用魚ロボットの開発
平田宏一
日本設計工学会平成13年度春期研究発表講演会講演論文集, p.69-72, (2001年5月).
 |
本報では,魚ロボットを高速化するための方法について検討し,高速化を目指した実験用魚ロボットの設計・試作を行う.さらに,実験用魚ロボットの尾ひれの周波数や振幅が遊泳速度及び消費電力に及ぼす影響を測定し,設計計算法の妥当性について検討する. |
| 52. |
船舶バリアフリーのための実験用車いすの開発
平田宏一,今里元信,宮崎恵子
日本設計工学会平成13年度春期研究発表講演会講演論文集, p.103-106, (2001年5月).
 |
本報では,手動車いすの基本的な運動特性を把握するために開発した実験用車いすについて報告する.さらに,実験用車いすを用いて,傾斜装置における走行実験を実施し,手動車いすの基本特性の測定を試みた.
|
| 53. |
船内における車いすの走行限界の把握
今里元信,阿曽薫,宮崎恵子,平田宏一,太田進
平成13年度(第1回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p.233-236(2001年6月).
 |
本報では,車いすの走行限界を把握するための研究の流れを示し,当所でこれまでに行っている研究について述べる。 |
| 54. |
計測用車いすの開発
平田宏一,今里元信,宮崎恵子
平成13年度(第1回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p.241-242(2001年6月).
 |
本報では,手動車いすの基本的な運動特性を把握するために開発した計測用車いすについて報告する。
|
| 55. |
斜面上における車いすの操作限界と負担感に関する調査
宮崎恵子,平田宏一,今里元信,太田進
平成13年度(第1回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p.247-250(2001年6月).
|
本研究の最初の段階として、斜面における手動車いすの走行実験をおこなった。本報では、本実験で実施したアンケート結果並びに車いすの駆動トルクや走行軌跡等の計測結果に基づき、斜面にて手動車いすを操作する場合の操作限界や負担感について検討した。
|
| 56. |
船舶における手動車いす走行の評価指標
宮崎恵子,平田宏一,今里元信
リハ工学カンファレンス2001,p. 169-172(2001年8月). |
著者らは、船舶における車いす走行に関する研究の第一段階として、静的傾斜条件下での想定通路上の手動車いす走行実験をおこなった。本稿では、その走行実験結果を解析し、手動車いす走行の評価指標について検討する。 |
| 57. |
50 W級小型スターリングエンジンの性能特性(その3,ロンビック機構に関する考察と性能試験)
平田宏一
日本機械学会第5回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.19-22(2001年10月).
 |
本報では,ピストン駆動機構に採用しているロンビック機構について検討する。そして,実験用エンジンの様々な改造を試み,運転試験を実施する。 |
| 58. |
魚ロボット用セミフリーピストン形スターリングエンジンの性能特性
平田宏一
日本機械学会第5回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.23-26(2001年10月).
 |
本報では,実験用小型エンジンにパワーピストンのストロークや作動ガス圧力,温度等を測定する装置を取り付け,本エンジンの基本性能を測定する。さらに,別途開発を進めている電気モータを用いた魚ロボットの実験結果に基づき,本エンジンを魚ロボットに利用した場合の遊泳速度について検討する。
|
| 59. |
模型スターリングエンジンボートの製作とその教材化
平田宏一
日本機械学会第5回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.97-98(2001年10月).
 |
著者らは,今までにいくつもの模型エンジンやそれを載せた模型ボートを製作してきた。本報では,模型スターリングエンジンボートを製作するための要点と製作例について概説する。さらに,もの作り教育における教材としての適用性について検討する。
|
| 60. |
バリアフリー旅客船に関する一考察
宮崎恵子,平田宏一,今里元信,太田進,疋田賢次郎,池本義範
日本機械学会第10回交通・物流部門大会講演論文集,p.333-336(2001年12月). |
本稿では,中・小型を中心とした内航旅客船に適したバリアフリー設備の開発や,バリアフリー船に適した各設備の配置を求めることを目指して,旅客船に存在するバリアとそれを解決するための課題について検討する。 |
| 61. |
旅客船内における車いすの利用について
今里元信,宮崎恵子,平田宏一,太田進
日本機械学会第10回交通・物流部門大会講演論文集,p.337-340(2001年12月). |
実際の船舶において,車いすが安全に走行できるか否かを判定するためには,多くの加速度条件を想定する必要があり,実験だけでは困難であることから,任意の加速度条件下において車いすの走行を模擬できるプログラムを開発中である。本報では,そのための基礎的なモデルを構築したことおよび今後の課題について述べる。
|
| 62. |
船舶バリアフリーのための模型車いすの開発
平田宏一,牧田安弘,榊原寛明,河野哲平,御法川学
日本機械学会第10回交通・物流部門大会講演論文集,p.341-342(2001年12月).
 |
著者らは縮尺1/3 の模型車いすの開発を進めており,手動車いすの走行特性の測定を試みている。本報では,試作した模型車いすについて概説し,傾斜路面において横断走行を行った走行試験について述べる。 |
| 63. |
多用途化を目指したユニット式魚ロボットの開発
平田宏一,河合秀祐(日立製作所)
日本設計工学会平成14年度春期研究発表講演会講演論文集, p.115-118, (2002年5月).
 |
実際の海中には,様々な種類の魚が生活している.それぞれの魚は,体形や運動形式が異なり,それぞれ特有の遊泳能力を持つ。それらの特徴を活かして魚ロボットを設計することで,様々な用途に使用可能な魚ロボットを開発できると考えられる。本報では,これらの観点から,高性能化・多用途化を目指して,各構成要素をユニット化した全長約1 mの魚ロボットを開発する。 |
| 64. |
魚ロボット用スターリングエンジンに関する基礎研究
平田宏一
日本機械学会第8回動力・エネルギー技術シンポジウム講演論文集,p. 625-628,(2002年6月).
 |
本報では,魚ロボット用動力源として検討している特殊なスターリングエンジンについて概説し,その基本特性を測定するために開発した実験用エンジンの性能特性について述べる。さらに,本エンジンのシミュレーション計算を行い,魚ロボットへの適用性について考察する。
|
| 65. |
車いすと群集流の避難シミュレーション
松倉洋史,勝原光治郎,宮崎恵子,池本義範,今里元信,太田進,疋田賢次郎,宮田修,桐谷伸夫,平田宏一
平成14年度(第2回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p. 233-237(2002年6月). |
海上技術安全研究所では、「車いすと群集流の相互干渉に関する調査」を実施した。この研究は、実験とシミュレーションによって車いすと群集流の相互干渉時の挙動とその内的メカニズムを明らかにすることを目的としたものである。本報告では、上記研究の実験結果をもとに、車いすと群集流の避難シミュレーションについて検討した結果を述べる。
|
| 66. |
多用途化を目指したユニット式魚ロボットの開発
平田宏一,河合秀祐(日立製作所)
平成14年度(第2回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p. 381-382(2002年6月).
 |
本報では、高性能化・多用途化を目指して開発した、全長約1 mのユニット式魚ロボットについて概説する。 |
| 67. |
車いすと群集流の避難実験
宮崎恵子,今里元信,池本義範,太田進,疋田賢次郎,勝原光治郎,松倉洋史,宮田修,桐谷伸夫,平田宏一
平成14年度(第2回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p. 383-386(2002年6月). |
当所では、国土交通省海事局安全基準課から調査研究を受託し、「車いすと群集流の相互干渉に関する研究」を実施した。本稿では、このうち、実験について述べる。
|
| 68. |
模型車いすの走行特性
平田宏一,牧田安弘(キャノン),榊原寛明(旭テック)
平成14年度(第2回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p. 387-390(2002年6月).
 |
車いすの基本特性を調べる実験ツールとして、2種類の車いす模型を開発した。 |
| 69. |
車いす走行補助装置の開発(その1 自動ブレーキ制御機構の設計・試作)
平田宏一,宮崎恵子,河野哲平(川崎重工)
平成14年度(第2回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p. 391-392(2002年6月).
 |
船舶のような動揺条件下において、手動車いすで安定した走行をおこなうには、操作に困難を伴う。本研究では、動揺条件下での手動車いすの移動を安全かつ快適にすることを目的とした走行補助装置の開発を進めている。本報では、簡易的な走行補助装置として試作した自動ブレーキ制御機構について述べる。
|
| 70. |
小型化・低コスト化を目指した実験用スターリングエンジンの開発
平田宏一
日本機械学会2002年度年次大会講演論文集,Vol.IV,p.155-156(2002年9月).
 |
本報では,小型・軽量化,低コスト化を目指した実験用エンジンの開発状況並びに実験結果について述べ,スターリングエンジンの小型化・低コスト化について考察する。 |
| 71. |
熱交換器の簡素化と高効率化を目的とした新形式の外燃機関について
汐崎浩毅,平田宏一
日本機械学会第6回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 3-6(2002年10月). |
本報で紹介する機関は,特に加熱・冷却両熱交換器における十分な伝熱量の確保,熱交換器の簡素化といった面で原理的な長所を持つ機関として構成している。 |
| 72. |
20,000 kW級船舶用スターリングエンジンの検討
平田宏一
日本機械学会第6回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 21-22(2002年10月).
 |
従来から開発されてきた実用スターリングエンジンは,数kW〜数十kW程度の出力レベルであり,大型舶用ディーゼルエンジンに匹敵するような,大出力のスターリングエンジンが実際に開発されたことはない。本報では,スターリングエンジンの大出力化に着目し,相似則や簡易的な伝熱計算の結果に基づき,出力20,000 kWの船舶用スターリングエンジンの概念設計を試みる。 |
| 73. |
ハーメティック形スターリングエンジンの性能特性
平田宏一
日本機械学会第6回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 39-42(2002年10月).
 |
発電用スターリングエンジンの出力向上を目指す場合,発電機をクランクケースに内蔵したハーメティック形式とすることが極めて有効であると考えられる。本報では,実験用小型スターリングエンジン"Ecoboy-SCM81"をハーメティック形式に改造する。さらに,その基本性能を測定し,ハーメティック形スターリングエンジンの有用性について考察する。 |
| 74. |
手動車いす用走行補助装置の開発
平田宏一,高田康夫,御法川学
日本機械学会第11回交通・物流部門大会講演論文集,p. 301-302(2002年12月).
 |
船舶のような動揺条件下において,手動車いすで移動することは非常に困難であり,しかも危険を伴う。本研究では,動揺条件下での手動車いすの移動を安全かつ快適にすることを目的とした走行補助装置の開発を進めている。本報では,手動車いすの左右後輪の間に差動制限機構を取り付けた走行補助装置について述べる。 |
| 75. |
加速度条件下における車いす操作モデルの開発
今里元信,平田宏一,阿曽薫,宮崎恵子,太田進
日本機械学会第11回交通・物流部門大会講演論文集,p. 303-306(2002年12月). |
「船内車いす走行モデル」を構築するためには,前報で開発した「走行モデル」に加え,車いすに作用させる駆動力を与えるモデルを開発する必要がある.そのためには,人間の漕ぎ方をモデル化した「操作モデル」の構築が必要である.本報では,「船内車いす走行モデル」を構築するために,「操作モデル」を開発し,車いす重心位置の軌跡を導いたことについて述べる.
|
| 76. |
魚ロボットの上下運動メカニズムに関する研究
櫻井健太郎,平田宏一,長松昭男,御法川学
日本機械学会関東学生会第42回学生員卒業研究発表講演会講演前刷集,p.97-98,(2003年3月).
 |
本研究では、魚ロボットの3次元運動(前進、旋回、上下運動)に着目し、様々な上下運動方法を検討する。そして、上下運動メカニズムを持つ実験用魚ロボットを設計・製作し、その運動性能について考察する。
|
| 77. |
上下運動機構を有する魚ロボットに関する研究
平田宏一
第12回アクアバイオメカニズム研究会資料,p.9,(2000年3月)
 |
本報では,魚ロボットの上下運動に着目し,フィンの揚力,重心移動及び尾部の上下方向への関節を利用した3種類の実験用魚ロボットについて概説する。 |
| 78. |
車いす走行補助装置の開発(その2 差動制限機構を利用した車いす走行補助装置の特性)
平田宏一,宮崎恵子,高田康夫
平成15年度(第3回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p. 393-394(2002年6月).
 |
前報では、簡易的な傾斜角センサとマイコンを利用した自動ブレーキ制御機構を設計・試作し、その特性を調べた。本報では、新たな走行補助装置として、手動車いすの左右後輪の間に差動制限機構を取り付けた走行補助装置の開発を試みる。 |
| 79. |
帆装船用複合帆の空力特性
藤原敏文,上野道雄,二村 正,平田宏一
平成15年度(第3回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p. 141-146(2002年6月). |
| 80. |
フリーピストンスターリングエンジンの簡易性能予測法
星野 健,平田宏一
日本機械学会第7回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 9-12(2003年10月). |
本研究ではリニア発電機を備えたフリーピストンスターリングエンジンについて,初期設計に使用できるようあまり複雑にならず,かつエンジン性能を比較的良く予測できる解析モデルの検討を行った. |
| 81. |
小型スターリングエンジンの機械損失低減技術
平田宏一
日本機械学会第7回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 75-76(2003年10月).
 |
前報では,ハーメティック形式に改造した100 W級スターリングエンジン"Ecoboy-SCM81"を運転し,その有用性について確認した。本報では,さらなる機械損失の低減を目指して,摺動部に二硫化モリブデンショット処理(以下,MoS2ショット処理と称す)を施し,簡易的な性能試験より,その有用性について調べた。 |
| 82. |
マンタ型魚ロボットの設計・試作
菱沼和久,金野祥久,平田宏一,川田正國,日本機械学会関東支部第10期講演会講演論文集,p.109-110(2004年3月).
 |
本研究では、できる限り滑らかな上下運動を実現させるために、胴体全体の断面形状が翼型に似て、流体力のみで泳いでいると推測されるマンタをモデルにした実験用魚ロボットを設計・試作し、遊泳試験および考察を行う。 |
| 83. |
健常者の車椅子操作時の筋活動及び動作特性
中村孝文,北濱由佳,田内雅規,平田宏一,宮崎恵子
人間工学会誌,第40巻特別号(日本人間工学会第45回大会講演集),p.414-415(2004年6月). |
| 84. |
高度船舶安全管理システムに関する技術要件
西尾 澄人,平田 宏一,沼野 正義,塚原 茂司
平成16年度(第4回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p.305-306,(2004年7月).
 |
| 85. |
バリアフリー機器の開発 ─変速機構付手動車いすの設計・試作─
平田宏一,川田正國,宮崎恵子,平成16年度(第4回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p.
313-314(2004年7月).
 |
本報では、手動車いすの操作性及び機能性を向上させることを目的とし、フリクションドライブ機構を利用した変速機構付手動車いすの設計・試作を行った。
|
| 86. |
バリアフリーフェリーにおける模擬車いす利用者を含んだ避難実験
宮崎恵子,平田宏一,平成16年度(第4回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p.
315-316(2004年7月).
 |
本稿では、非常時対応の現状、模擬車いす利用者を含む避難実験の概要、並びに車いす利用者を含む旅客の避難経路を求めるための避難シミュレーションについて述べる。 |
| 87. |
実験用マンタ型魚ロボットの遊泳性能
菱沼和久,金野祥久,平田宏一,川田正國,日本機械学会2004年度年次大会,p.149-150(2004年9月).
 |
本報では、ヒレのピッチ運動のみで推進、旋回および上下運動を可能とするマンタ型魚ロボットを用いて、その遊泳速度、旋回運動、上下運動、および操作特性に関する試験結果について報告する。 |
| 88. |
位相差可変スターリングエンジンの基本特性
平田宏一,川田正國,横川嘉徳,山下巌,日本機械学会第8回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.
63-64(2004年10月).
 |
本報では,工場等からの排熱を利用するスターリングエンジン発電システムを想定し,排熱の熱量や温度の変動に応じて,運転パラメータの制御が可能な位相差可変機構を有する実験用スターリングエンジンについて概説する。さらに,排熱を模擬した高温空気を熱源に用いた場合のエンジン特性を測定した結果について述べる。 |
| 89. |
多種熱源を利用可能なスターリングエンジンに関する研究
高田康夫,御法川学,平田宏一,川田正國,日本機械学会第8回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.
9-12(2004年10月).
 |
本研究では,廃熱やバイオマス利用を想定したスターリングエンジンの設計手法を検討する。また,出力100
W程度の実験用スターリングエンジンを設計・試作し,設計手法の妥当性について考察することを目的としている。本報では,多段化したスターリングエンジンの性能試算結果並びに実験用エンジンの概要について述べる。 |
| 90. |
ハーメティック形マイクロスターリングエンジンの設計・試作
平田宏一,川田正國,日本機械学会第8回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.61-62(2004年10月).
 |
本報では,スターリングエンジンの小型化・高出力化を実現する一つの手法として,作動ガスの高圧化に着目する。そして,模型エンジンと同等の簡単な構造を有する小型スターリングエンジンを圧力容器構造とすることで,小型・高出力エンジンの開発を試みるとともに,高圧機器設計における課題について考察する。 |
| 91. |
無段変速機構を有する手動車いすの開発
平田宏一,川田正國,宮崎恵子,日本機械学会第13回交通・物流部門大会講演論文集,p.
281-282(2004年12月).
 |
本研究では,バリアフリー化推進を目指し,新たなバリアフリー機器の開発を試みている。そして,手動車いすの操作性及び機能性を向上させることを目的とし,フリクションドライブ機構を利用した変速機構付手動車いすの設計・試作を行った。 |
| 92. |
避難シミュレーションを用いたバリアフリーフェリーの避難経路の検討
宮崎恵子,平田宏一,日本機械学会第13回交通・物流部門大会講演論文集,p.
283-284(2004年12月).
 |
著者等は、さらなるバリアフリー化の推進には、身体障害者等を考慮した避難・誘導を検討する必要があると考え、バリアフリー化旅客船の非常時の安全性向上に関する研究を実施し、避難経路を検討するための避難シミュレーションを開発している。本稿では、非常時対応の現状を示すとともに、避難シミュレーションプログラムを用いて車いす利用者を含む旅客の避難経路を検討する。 |
| 93. |
スターリングエンジンの船舶分野への適用可能性
平田宏一,川田正國,第73回マリンエンジニアリング学術講演会,p.107-108(2005年5月).
 |
本報で述べるスターリングエンジンは,ディーゼルエンジンよりも古くに発明され,発展と低迷を繰り返しながら開発が進められてきた外燃機関である。以下,低公害性・燃料の多様性など,環境調和性に優れた特徴を持つスターリングエンジンの船舶分野への適用可能性について考察する。 |
| 94. |
実験用ウミガメ型海中ロボットの設計・試作
古屋拓郎,金野祥久,水野明哲,菱沼和久,平田宏一,川田正國,日本設計工学会2005年度春季研究発表講演会講演論文集,p.105-108(2005年5月).
 |
本研究では,海中ロボット開発における羽ばたき型推進の有効性を検討するため,ウミガメをモデルとした実験用ウミガメ型海中ロボットを設計・試作し,性能評価を行う. |
| 95. |
介助用車いすの駆動機構に関する研究
原秀貴,御法川学,平田宏一,川田正國,日本設計工学会2005年度春季研究発表講演会講演論文集,p.125-128(2005年5月).
 |
本研究では,介助者の負担を減らすことができる介助用車いすの開発を目的とする.以下,車いすのシートを持ち上げる機構を設計・試作し,その駆動機構の有効性を考察する. |
| 96. |
実験用多段式スターリングエンジンの基本性能
平田宏一,川田正國
日本機械学会第9回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.15-18(2005年10月).
 |
一般に工場等からの排熱は化石燃料の燃焼と比べて温度が低い。そのような観点から,前報では,行程容積を適切に調整したスターリングエンジンを多段に配置することで排熱のエネルギーを有効に利用するエンジン形式を提案した。本報では,試作した実験用多段式スターリングエンジンについて概説し,初期の運転試験結果について報告する。 |
| 97. |
スターリングエンジンを用いた内航船用排熱回収システムの提案
平田宏一,加納敏幸,川田正國,赤澤輝行,井上敏彦,飯田光利
日本機械学会第9回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.97-98(2005年10月).
 |
港湾に停泊している船舶のディーゼルエンジンから放出される排ガスは,港湾地域の大気環境汚染の原因となっている。本報で提案する排熱回収システムは,港湾地域の環境汚染を改善することを目的とし,運航中の推進に使うディーゼルエンジンの排熱エネルギーをスターリングエンジンによって回収し,電気として蓄え,停泊中の船内電力に使用する。したがって,船舶が停泊している際,発電用ディーゼルエンジンの運転が不要となり,港湾地域の環境汚染が改善され,クリーンな地域環境を保つことができる。 |
| 98. |
洋上風力発電による代替燃料製造システム(燃料ガス貯蔵のための反応熱の有効利用)
矢後 清和,大川豊,日根野元裕,高野宰,平田宏一
日本機械学会第9回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.99-100(2005年10月). |
| 99. |
高効率スターリングエンジンの開発
赤澤輝行,村尾景司,平田宏一,星野健
日本機械学会第9回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.105-106(2005年10月). |
| 100. |
スターリングエンジンの強度設計(模型エンジンから実用エンジンへの展開)
川田正國,平田宏一
日本機械学会第9回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p.127-128(2005年10月).
 |
本報では、従来の模型エンジンの寸法形状と同程度でありながら、より大きな出力が得られるようなエンジンの構造設計について考える。ここでは設計の基本である圧力容器構造としての強度計算における基本的な項目について考察する。 |
| 101. |
無線LANを利用した旅客船用情報提供システムの提案
平田宏一,宮崎恵子,川田正國
日本機械学会第14回交通・物流部門大会講演論文集,p. 401-402(2005年12月).
 |
昨今,交通機関のバリアフリー化が活性化されており,高齢者・障害者の活動の場が急速に拡大している。そのような背景に伴い,旅客船においては,高齢者や障害者を含む全ての乗客を対象とした,旅客ターミナルや旅客船内の情報提供システムの構築が望まれている。本報では,安価な旅客船用情報提供システムの開発を目的とし,既存のハードウェアを流用した簡易システムを提案する。本システムは,パソコンを用いたWEBサーバと無線LAN機器で構成され,旅客は市販の情報端末機(PDA)を使用する。特別な機器開発をすることなく,システムを構築できるという特徴がある。 |
| 102. |
避難シミュレーションを用いた高齢者等の船舶内避難経路の検討
宮崎恵子,平田宏一
日本機械学会第14回交通・物流部門大会講演論文集,p. 399-400(2005年12月). |
| 103. |
よみがえるスターリングエンジン
平田宏一
平成17年度(第5回)海上技術安全研究所講演会講演集,p. 45-52(2006年1月).
 |
本報では,スターリングエンジンの基本構造と特徴,さらに原理の発明から現在に至るまでの発展経緯について概説する。そして,当研究所で進めてきたスターリングエンジンに関連した研究を踏まえて,現在の関連技術を紹介する。さらに,平成17年度より開始しているスターリングエンジンを用いた内航船舶用排熱回収システムの開発研究の概要を紹介する。 |
| 104. |
羽ばたき推進性能測定装置の開発
川野健,金野祥久,平田宏一,川田正國
日本機械学会関東支部第12期総会講演会講演論文集,p.163-164(2006年3月). |
| 105. |
港湾内の環境保全を目指した内航船舶用排熱回収システムの開発
平田宏一
平成18年度(第6回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p.157-158(2006年7月).
 |
400℃程度の低温排熱を有効利用する技術は,あらゆる方式において確立されていないのが現状である。本研究では,400℃程度の低温排熱を利用するスターリングエンジンを開発し,発電・蓄電を可能とする実証用システムを構築する。 |
| 106. |
排熱利用スターリングエンジンの開発並びに性能特性
平田宏一,今井康之,川田正國,赤澤輝行,坂口諭
平成18年度(第6回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p.263-264(2006年7月).
 |
運航中のディーゼルエンジンから放出される排熱を回収する技術は,エネルギーの有効利用あるいは環境保全の観点から極めて有望である。平成17年度より開始された(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構
基礎的研究推進制度「港湾内の環境保全を目指した内航船舶用排熱回収システムの開発」において,著者らは,400℃の高温熱源で運転する目標出力500
Wの実験用スターリングエンジンを設計・試作し,その性能評価を開始した。以下,開発を進めている実験用スターリングエンジンについて報告する。 |
| 107. |
スターリングエンジンに用いるセラミックス製熱交換器の開発
平田宏一,今井康之,川田正國,赤澤輝行,村尾景司
平成18年度(第6回)海上技術安全研究所研究発表会講演集,p.265-266(2006年7月).
 |
本研究では,スターリングエンジンの高効率化と普及を目指して,高温条件下で使用が可能なセラミックス製ヒータの開発を進めている。本報では,試作したセラミックス製ヒータ並びにその性能を評価するために開発した評価用スターリングエンジンについて概説する。 |
| 108. |
内航船舶に用いる排熱利用スターリングエンジンの開発
平田宏一,今井康之,川田正國,赤澤輝行,坂口諭
日本機械学会,2006年度年次大会講演論文集,Vol.3,p.321-322(2006年9月).
 |
本研究では,400℃程度の低温排熱から有効な電力を取り出すための排熱利用スターリングエンジンを開発し,内航船舶に用いる排熱回収システムの開発を目指している。以下,本排熱回収システムの概略並びに現在開発を進めている実験用スターリングエンジンの構造並びに性能特性について報告する。 |
| 109. |
セラミックス製熱交換器を用いたスターリングエンジンの開発
平田宏一,今井康之,川田正國,赤澤輝行,村尾景司
日本機械学会,2006年度年次大会講演論文集,Vol.3,p.323-324(2006年9月).
 |
本研究では,スターリングエンジンの高効率化並びに普及を目指して,セラミックス製ヒータの開発を進めている。そして,試作したセラミックス製ヒータを評価用スターリングエンジンに搭載し,その基本性能を調べ,耐熱性・耐圧性を含めた実機への適用可能性を検討している。 |
| 110. |
スターリングエンジンを用いた排熱回収システムの開発(第1報 実験用エンジンの設計・試作並びに性能特性)
平田宏一,今井康之,川田正國,赤澤輝行,坂口諭
日本機械学会第10回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 97-100(2005年10月).
 |
港湾に停泊している船舶のディーゼルエンジンから放出される排ガスは,港湾地域の大気環境汚染の原因となっている。著者らは,その解決方法の一つとして,運航中のディーゼルエンジンから放出される排熱をスターリングエンジン発電機によって回収し,電気エネルギーとして蓄えるシステムを提案している。本報では,2005年度に設計・試作した実験用スターリングエンジンについて概説し,ディーゼルエンジンの排ガスを模擬した高温空気による運転結果について報告する。そして,実験結果と等温モデルシミュレーションとを比較し,エンジンの性能評価を行う。 |
| 111. |
セラミックス製熱交換器評価用スターリングエンジンの開発
平田宏一,今井康之,石村惠以子,川田正國,赤澤輝行,村尾景司
日本機械学会第10回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 105-108(2005年10月).
 |
従来のスターリングエンジンにおいて,エンジンの高効率化を図るためには,高温条件下での材料強度の制限から,ヒータ材料としてインコネルやハステロイX等の特殊なニッケル合金を用いてきた。本研究では,スターリングエンジンのさらなる高効率化を目指して,セラミックス製ヒータの実現可能性を検討している。本報では,セラミックス製ヒータを搭載した評価用スターリングエンジンの基本性能について述べる。 |
| 112. |
2シリンダ・ダブルアクティング形スターリングエンジンの開発
平田宏一
日本機械学会第10回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 93-96(2005年10月).
 |
従来から開発されてきたダブルアクティング形スターリングエンジンは,4本のシリンダから構成されるのが一般的であり,エンジン全体の部品数が増加することやピストン駆動機構が複雑になるなどの問題がある。そのような観点から,著者らは,2本のピストン・シリンダから構成される特殊なDA形スターリングエンジンを検討し,実験用エンジンを開発している。本報では,2シリンダ・ダブルアクティング形スターリングエンジンの特徴について述べ,実験用エンジンの性能試験結果の概略について報告する。 |
| 113. |
排熱利用スターリングエンジンに用いる熱交換器の伝熱性能評価
今井康之,平田宏一,川田正國,石村惠以子
日本機械学会第10回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 101-102(2005年10月). |
外燃機関であるスターリングエンジンはエンジン外部からの加熱・冷却により仕事を行うため、運転に必要な熱源は制約されない。著者らは舶用ディーゼルエンジンから放出される排熱に着目し、スターリングエンジンを用いた排熱回収システムを開発している。船舶用ディーゼルエンジンの排熱は比較的温度が低いため、最大限の排熱をスターリングエンジン内に取り込むためには、高性能な高温熱交換器(ヒータ)を開発し、膨脹空間ガス温度を高めることが重要となる。本報では、ヒータに着目した伝熱計算の結果と実験用スターリングエンジンの測定結果とを比較・検討することにより、ヒータの性能評価を行う。 |
| 114. |
家庭用コジェネレーション向けスターリングエンジンの開発
赤澤輝行,村尾景司,平田宏一,星野健,北英紀
日本機械学会第10回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 103-104(2005年10月). |
| 115. |
スターリングエンジンに用いるスコッチ・ヨーク機構のトライボロジ
川田正國,平田宏一,今井康之,石村惠以子
日本機械学会第10回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 55-56(2005年10月).
 |
著者らは船舶用ディーゼルエンジンの排熱を高温熱源として動作するスターリングエンジンを開発している(1)。本エンジンは従来と比較して低い温度の熱源を利用することから,その目標性能を達成するにはピストンシールや機構の摩擦に起因する機械損失の軽減は開発課題の一つである。
本報では,平成17年度に開発した実験用スターリングエンジンを用いて500時間の基本性能試験を行い,スコッチ・ヨーク機構の摩耗特性と表面性状について調べたので,その結果を報告する。
|
| 116. |
ハーメティック形マイクロスターリングエンジンのCAE解析
石村惠以子,川田正國,平田宏一,今井康之
日本機械学会第10回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 57-58(2005年10月). |
著者らはスターリングエンジンの小型化・高出力化を目指して、設計圧力を10
MPaとした小型スターリングエンジンの設計・試作を進めてきた1)。本エンジンを設計する際には、CAE解析を用いず、従来の材料力学に基づく高圧容器の設計手順に従った。そして、圧力容器部材を試作した後、油圧試験により、各部材の変形量を測定した。本報では、本エンジンの主要部品のCAE解析を行い、部品単体並びにエンジンを組み立てた状態での解析結果から、CAE解析をエンジン設計に利用する際の留意点について考察する。 |
| 117. |
スターリングエンジンの動特性について
塚原茂司,土屋一雄,松本怜,清水優一朗,平田宏一,川田正國
日本機械学会第10回スターリングサイクルシンポジウム講演論文集,p. 59-60(2005年10月). |
| 118. |
避難シミュレーションを用いた高齢者等の船舶内避難経路の検討(第2報 乗客特性の影響)
宮崎恵子,平田宏一,今井康之
日本機械学会第14回交通・物流部門大会講演論文集,(2006年12月). |
| 119. |
内航船舶用排熱回収システムにおける排気管流路の圧力損失
石村惠以子,平田宏一,今井康之,川田正國
日本機械学会関東支部第13期総会講演会講演論文集,p.343-344(2007年3月).
 |
本排熱回収システムは、ディーゼルエンジンの排気管流路中にスターリングエンジンの熱交換器を組み込むものである。それによって生じる圧力損失はディーゼルエンジンの過給機の運動に影響するため、ディーゼルエンジンの出力性能に与える影響は大きい。本報では、排熱回収スターリングエンジンを当研究所内のディーゼルエンジンの排気管流路に組み込んだ場合の圧力損失の実験結果を報告するとともに、CFD解析による計算結果との比較・検討を行う。さらに、それらの結果を踏まえて実船実験に使用する排熱回収システムの排気管流路について検討する。 |
| 120. |
内航船舶用排熱回収システムに用いる実験用スターリングエンジンの性能特性
平田宏一,西尾澄人,石村惠以子,今井康之,川田正國
日本機械学会関東支部第13期総会講演会講演論文集,p.345-346(2007年3月).
 |
港湾に停泊している内航船舶のディーゼルエンジンから放出される排ガスは,港湾地域の大気環境汚染の原因となっている。著者らは,その解決策の一つとして,運航中のディーゼルエンジンから放出される排熱をスターリングエンジン発電機によって回収する排熱回収システムの開発を進めている。本報では,当研究所内に設置されている舶用ディーゼルエンジンの排ガスを熱源としたスターリングエンジンの運転結果並びに各エンジンのエネルギーバランスについて報告する。 |
|
|
|
| ●その他 |
| 1. |
教材用エンジンの設計・試作(高温度差形)(講義)
平田宏一
日本機械学会エンジンシステム部門, 講習会:模型スターリングエンジンのつくり方と教育への利用,p.21-30,2000年8月.
 |
本章では,新しい発想の模型スターリングエンジンを設計することに焦点を当て,発想から設計までの留意点について述べる。さらに,著者が設計・試作したいくつかの模型エンジンを紹介する。 |
| 2. |
生き物から学ぶメカニズム −魚ロボットを通して−(講義)
平田宏一
第2回桐蔭横浜大学工学部産学交流シンポジウム,2001年10月.
 |
海の中では,多くの魚が上手に泳いでいる。その泳ぎを応用することで,海中を自由に動き回ることができる海中作業ロボットの開発が可能となると考えられる。そこで,高性能な海中ロボットの実現を目指して,魚ロボットの開発研究を進めている。
|
| 3. |
スターリングエンジンの概要と開発事例(講義)
平田宏一
日本機械学会エンジンシステム部門,講習会:実用性から見たスターリングエンジンの将来展望,p.1-8,2003年1月.
 |
スターリングエンジンは,高熱効率性,低公害性,使用熱源の多様性などの優れた特徴を持つ外燃機関である。このエンジンは,1816年に発明されて以来,幾度かの発展と低迷を繰り返しながら高性能化・実用化への挑戦が試みられてきた。そして,省エネルギーや環境汚染が深刻な社会問題となっている現在,スターリングエンジンへの期待が再び高まってきている。
|
| 4. |
海上技術安全研究所におけるスターリングエンジンの研究(講義)
平田宏一
日本機械学会エンジンシステム部門,講習会:実用性から見たスターリングエンジンの将来展望,p.62-63,2003年1月.
 |
海上技術安全研究所(旧船舶技術研究所)では,1970年頃からスターリングエンジンの研究を進めてきた。主な研究項目は,(1) ピストンリングの摩擦力とガス漏れの影響,(2) 熱交換器における圧力損失の影響,(3) スターリングエンジンの制御におけるエンジン動特性,(4) 海中動力用スターリングエンジン,(5) 小型スターリングエンジンの設計手法,(6) 特殊な熱交換器の開発等である。 |
| 5. |
魚ロボットに関する基礎的研究(報告)
平田宏一,他6名
海上技術安全研究所報告,第2巻,第3号,p.1-27,2003年1月.
 |
本報告は,平成11年度に実施した重点基礎研究「自己推進運動体の効率的水中推進に関する基礎的研究」並びに平成12年度以降に実施している一般研究の研究成果の一部をまとめたものである。 |
| 6. |
わかりやすい力学と機械強度設計法(講義)
平田宏一
ISS産業科学システムズ,2007年2月.
 |
本講義では,機械設計をこれから学ぼうとしている方々を対象として,力学や材料強度の基礎から実務的な機械強度設計までを考えます。機械設計において,力のつりあいや動力の伝達,さらに材料の強度についての知識が重要なのは間違いありません。しかし,実際の機械は,複数の部品が複雑に組み立てられ,単純な力学モデルに置き換えることは簡単ではありません。また,実際の設計現場では,全ての部品の強度計算をして,部品の形状や材料を決定するほどの時間の余裕はありません。 |
|
|
|
|
平田 宏一
E-mail:khirata@nmri.go.jp |
|
|
[ Hirata HOME ]
[ NMRI HOME ]
|
|
| このページに関するお問い合わせはkhirata@nmri.go.jpまでお願いします
|